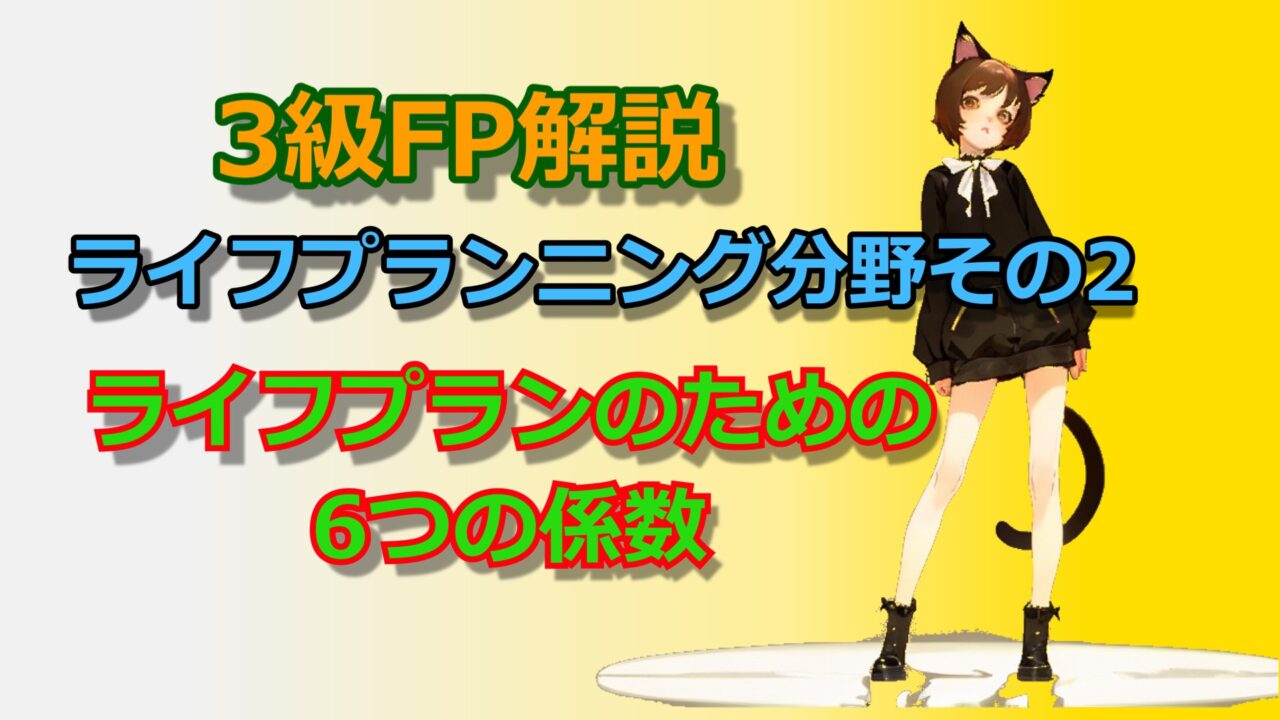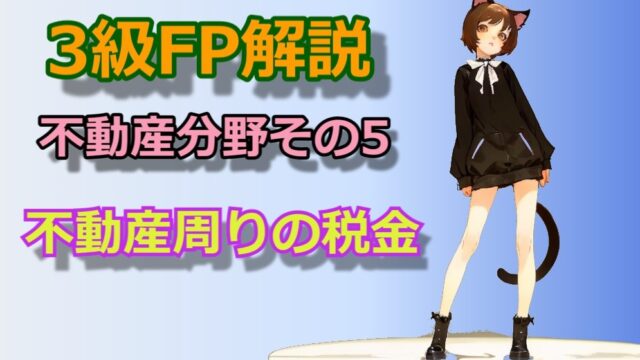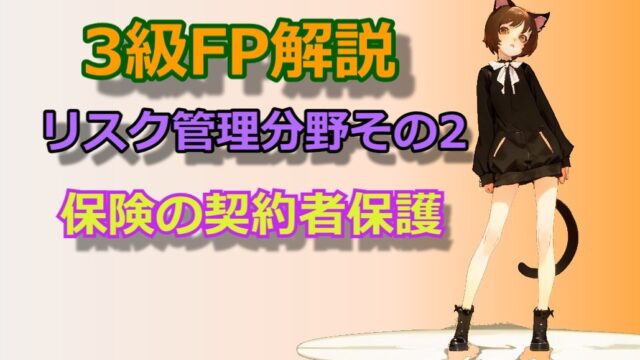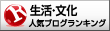今回はFP3級解説、ライフプランニング分野の第2回です。
前回はFPの行動規範とライフプランニングの流れについて解説しました。
今回は実際にライフプランニングを行うときに使う「係数」について解説していきます。
正直この係数を覚えるのは大変なのですが、大変なだけあって結構な頻度で問われるので、できればしっかり覚えておくことをおすすめしますよ。
Contents
いきなり「係数」とか言われても…。
で、この「係数」というのは何者で結局何に使うのかを簡単に説明すると、
「お金の皮算用をするために使う便利ツール」
です。
もう少し詳しく説明するとお金には
- 増やす(据え置いて利回りを得る)
- 貯める(収入を貯金に回す)
- 使う(取り崩す)
の3つのアクションを取りますよね?
そしてどのアクションを取るかに置いてそれぞれ、「現在」と「未来」の2点でその金額が違ってくるわけです。
現在いくらあるのかがわかっていて、「そのお金がある未来の時点でいくらまで増やせるのか」とか「そのお金を取り崩していくとしたらいくらずつ使えるのか」などの「未来のお金」を一発で計算できるツールがこの「係数」というわけですね。
逆に将来必要なお金がわかっている場合は、「運用するなら今いくらで始めればいいのか」など「現在のお金」を計算できる係数もあり、それらを合わせて6種類の係数が存在するということです。
そしてその係数は、
- 終価係数
- 現価係数
- 年金終価係数
- 減債基金係数
- 資本回収係数
- 年金現価係数
と名付けられており、それぞれ「利率」「期間」ごとに数字が設定されており、わかっている金額にその数字をかけることで必要な金額を求めることができるようになっています。
そして我々がやるべきことは、係数自体を求めることや係数を暗記することではありません。
| 係数 | 2% |
| 終価係数 | 1.2190 |
| 現価係数 | 0.8203 |
| 年金終価係数 | 10.9497 |
| 減債基金係数 | 0.0913 |
| 資本回収係数 | 0.1113 |
| 年金現価係数 | 8.9826 |
必要なのは、「用途に応じて適切な係数を一覧から選択し、掛け算をして必要な金額を算出する」だけです。
つまり、「どの係数を選べばいいのかを理解する」ことだけなんとかすれば答えはどうとでもなるということですので、あまり構えずに読み進めていただければいいかと思いますよ。
スポンサーリンク
6つの係数は3つのペアで覚える。
まずこの6つの係数なんですが、バラバラに覚えようとするとしっかり混乱するのでペアで覚えるようにしてください。
その組み合わせは、
- 「終価係数」と「現価係数」 → 「増やす」
- 「年金終価係数」と「減債基金係数」 → 「増やしながら貯める」
- 「資本回収係数」と「年金現価係数」 → 「増やしながら使う」
となっており、上で述べた「貯める」「増やす」「使う」のムーブとセットで覚えておくといいでしょう。
ここでの注意点はまず、「年金終価係数と年金現価係数はセットではない」ということですね。
終価係数と現価係数がセットなので、年金終価係数と年金現価係数もいかにもペアっぽい名前ですがここはセットではないことは覚えておくといいでしょう。
もう1つの注意点は、現在と未来が存在する以上「増やす」という能動的ではないムーブは全てのペアに絡んでくるということです。
なので、3ペアそれぞれが各1つの行為に該当するのではなく、
- 増えるだけで他は何もしない。
- 増えているのを横目に貯め続ける。
- 増えているのを横目に使っていく。
というイメージで分けるといいと思います。
ではそれぞれ見ていきましょう。
増えるのを眺めるだけ「終価係数」と「現価係数」。
まずは「増やす」だけを行った際の現在または未来の金額を求めるための係数である「終価係数」と「現価係数」についてです。
簡単に言うと、
- 利率と現在ある金額を元にちょっと増えた未来の金額を算出するのが「終価係数」
- 利率と未来の金額を元に現在必要なちょっと少ない金額を算出するのが「現価係数」
となります。
例を見ていきましょう。
例題
手元にある100万円を年利2%で10年間運用した場合、最終的にいくらになるか、下表の係数を用いて求めよ。
10年の係数一覧表
| 係数 | 2% |
| 終価係数 | 1.2190 |
| 現価係数 | 0.8203 |
| 年金終価係数 | 10.9497 |
| 減債基金係数 | 0.0913 |
| 資本回収係数 | 0.1113 |
| 年金現価係数 | 8.9826 |
この場合、手元の100万円を「使ったり追加したりせずにそのまま運用だけして10年後にちょっと増やす」ということですので、使用する係数は「終価係数」です。
終価係数・10年・2%の係数は「1.2190」ですので、手元の100万円に1.2190をかけて
1,000,000 × 1.2190 = 1,219,000
となり答えはそのまま 1,219,000円 となりますね。
要は使う係数さえ特定できてしまえばあとは掛けるだけで答えが出せる、非常に簡単な計算問題が出るということです。
もう1つ例題です。
例題
資金を年利2%で運用し10年後に100万円貯めたい場合、運用のために現在用意すべき資金はいくらか。下の係数を用いて求めよ。
10年の係数一覧表
| 係数 | 2% |
| 終価係数 | 1.2190 |
| 現価係数 | 0.8203 |
| 年金終価係数 | 10.9497 |
| 減債基金係数 | 0.0913 |
| 資本回収係数 | 0.1113 |
| 年金現価係数 | 8.9826 |
さっきと逆ですね。
この場合は10年後に100万円ほしいので、「使ったり追加したりせずに手元資金の運用だけで100万になるようなちょっと少ない金額」を算出したいので、使用する係数は「現価係数」です。
現価係数・10年・2%の係数は「0.8203」ですので、将来ほしい100万円に0.8203をかけて
1,000,000 × 0.8203 = 820,300
となり答えはそのまま 820,300円 となりますね。
こちらも係数さえ特定できてしまえばあとは掛けるだけで答えが出ます。
係数6つともこんな感じなので、「問題のパターンでどの係数を使うか決定する」プロセスがヤマ場ということですね。
以上が「終価係数」と「現価係数」ペアの解説でした。
増えるのを見ながら足していく「年金終価係数」と「減債基金係数」。
上述した2つの係数は単純に「増えていくのを眺めるだけ」というムーブでしたが、次のパターンは「追加で資金を貯めていく」というムーブが加わります。
このパターンで使う係数は以下の2つ、
- 決まった額を積み立てて運用し、最終的にいくらになるのかを求めるのが「年金終価係数」。
- 決まった目標金額を決めて、それに必要な運用資金の期間あたり積立金額を求めるのが「減債基金係数」。
です。
これをややこしくしているのはひとえに「利回り」の存在です。
利回りを考慮しなければ、最終的な金額は「年間の積立金額×年数(月の場合もあり)」で求められますし、必要な積立金額は「目標金額÷年数(こちらも月の場合あり)」で簡単に出せます。
これに積み立てたあとの金額に対しての利回りを加味したのが「年金終価係数」と「減債基金係数」というわけですね。
こちらも例題で見ていきましょう。
例題
年利2%で運用しながら年額40万円を10年間積み立てていった場合、最終的な元利合計金額はいくらになるか。下の表を用いて求めよ。
10年の係数一覧表
| 係数 | 2% |
| 終価係数 | 1.2190 |
| 現価係数 | 0.8203 |
| 年金終価係数 | 10.9497 |
| 減債基金係数 | 0.0913 |
| 資本回収係数 | 0.1113 |
| 年金現価係数 | 8.9826 |
この場合は積立金額がわかっていて最終的な金額を求めたいので、使用する係数は「年金終価係数」です。
この数字は表では10.9497ですので、
40万円 × 10.9497 = 4,379,880
で 4,379,880円 となります。
年間40万円を無利子で10年積み立てたら400万円ですので、プラス利息分と考えるとしっくりくる数字ですよね。
こんな感じで「積立金額+利息」を掛け算一発で出してくれるのが「年金終価係数」というわけです。
続いて逆のパターンの「減債基金係数」です。
こちらも例題を見てみましょう。
例題
年利2%で運用しながら積立を行い、10年後に500万円用意したい。この場合、年間でいくら積み立てる必要があるか。下の表を用いて求めよ。
10年の係数一覧表
| 係数 | 2% |
| 終価係数 | 1.2190 |
| 現価係数 | 0.8203 |
| 年金終価係数 | 10.9497 |
| 減債基金係数 | 0.0913 |
| 資本回収係数 | 0.1113 |
| 年金現価係数 | 8.9826 |
先ほどと逆で、最終的な目標金額が決まっていて積み立てる金額を求めたいケースです。
このパターンで使用するのが「減債基金係数」です。
減債基金係数は表では0.0913となっていますので、今までと同様、判明している数字にこれを掛けるだけです。
5,000,000円 × 0.0913 = 456,500
となり年間の積み立て必要金額は 456,500円 であることがわかります。
とにかく「積立」に関係しているのが「年金終価係数」と「減債基金係数」というふうに覚えて正しい係数を選べるようにしていきましょうね。
残りを増やしながら取り崩す「資本回収係数」と「年金現価係数」。
最後のペアは、「増えているのを眺めながら取り崩す」パターンで使う係数です。
こちらは、
- 今あるお金がわかっていて取り崩せる金額を求めるときに使う「資本回収係数」。
- 決まった額を取り崩していきたい場合に今必要な金額を求めるときに使う「年金現価係数」。
のペアです。
こちらもわかっている金額に正しい係数を掛ければ一発で求めることができます。
それぞれ例題を見ていきましょう。
例題
手元にある500万円を年利2%で運用しながら10年かけて取り崩した場合、年間で受け取れる金額はいくらか。下の表を用いて求めよ。
10年の係数一覧表
| 係数 | 2% |
| 終価係数 | 1.2190 |
| 現価係数 | 0.8203 |
| 年金終価係数 | 10.9497 |
| 減債基金係数 | 0.0913 |
| 資本回収係数 | 0.1113 |
| 年金現価係数 | 8.9826 |
この場合は今あるお金が500万円と判明しており、そこから10年で取り崩したら毎年いくら取り崩せるかを求めたいので、使用する係数は「資本回収係数」です。
表では資本回収係数は0.1113ですので、
5,000,000円 × 0.1113 = 556,500円
となり、毎年 556,500円 取り崩せることがわかります。
係数さえちゃんと選べてしまえば簡単ですね。
慣れてきたと思うのでサクサク進みましょう。次の例題です。
例題
年利2%で運用しながら10年かけて毎年50万円ずつ取り崩していく場合、必要な元手はいくらか。下の表を用いて求めよ。
10年の係数一覧表
| 係数 | 2% |
| 終価係数 | 1.2190 |
| 現価係数 | 0.8203 |
| 年金終価係数 | 10.9497 |
| 減債基金係数 | 0.0913 |
| 資本回収係数 | 0.1113 |
| 年金現価係数 | 8.9826 |
さっきの逆ですね。
取り崩したい金額がわかっていて必要資金を求めたいので使う係数は「年金現価係数」です。
これは8.9826となっていますので、
500,000円 × 8.9826 = 4,491,300
となり、必要な元手は 4,491,300円 だとわかります。
こんな感じで、「取り崩す」というムーブが出てきたら「資本回収係数」と「年金現価係数」のペアを使うと思っていただければいいかと思いますよ。
月の返済金額とか借入金額とかを求める場合ですね。
係数の基本的な解説については以上です。
スポンサーリンク
本番で忘れてしまったときに使える小技。
で、この6つの係数ですが、小難しい名称とともにいっぺんに出てくるため覚えづらかったり本番で迷ってしまうことがあります。
そんなときに苦肉の策として使える小技のようなものを少し紹介します。
ただ前提として「覚えてたほうが早い」のは事実ですので、これがあれば覚えなくていいというわけではないことをご承知おきください。
また、この小技を使うには
「問題文を読んで理解していること」
が必須となっています。
問題文を読んでもイメージができる状態になっていなければ意味はありませんので、「どんな状況からでも答えを導き出せる超ウルテクではない」ということはご理解くださいね。
終価係数を電卓で計算してしまう。
まず、基本ペアの「終価係数」と「現価係数」で使える小技です。
前回の解説の中で「変動率」周りについて解説した際に、「◯年後の金額を電卓で算出」というやり方に触れました。

要は「変動率を加味した◯年後の金額」とは「利回りで運用した合計金額」と同義なんですね。
なので上で書いた終価係数の例題で言うと、
「1.02」「×」「=」「=」「=」「=」「=」「=」「=」「=」「=」(10年なので「=」を9回)
で終価係数の近似値が出てきます(シャープ電卓の場合)。
この計算で出た数字と一番近い数字を表から選んで使えばいいということですね。
そして「現価係数」についてですが、こちらは「終価係数の逆数」となっていますので、終価係数を電卓で出したあと、
「÷」「=」
と押すと逆数がでて現価係数の近似値が計算できます(こちらもシャープの場合)。
この数字に近い数値になっている係数を使えばいいということですね。
一旦利回りを無視して計算してみる。
もう1つの方法は少し解像度が下がってしまいますが、終価係数と現価係数を除く4種類どれでも高確率で答えが出せる小技です。
係数がどうしても覚えられない場合、思い切って利回りを全無視して計算してみるというやり方があります。
こうすると計算は単純な掛け算や割り算になるのでそれに近い数字を選ぶことで答えになんとかたどり着けるという算段です。
先程の例題を見てみましょう。
例題
年利2%で運用しながら10年かけて毎年50万円ずつ取り崩していく場合、必要な元手はいくらか。下の表を用いて求めよ。
10年の係数一覧表
| 係数 | 2% |
| 終価係数 | 1.2190 |
| 現価係数 | 0.8203 |
| 年金終価係数 | 10.9497 |
| 減債基金係数 | 0.0913 |
| 資本回収係数 | 0.1113 |
| 年金現価係数 | 8.9826 |
こちらの問題は知っていれば「年金現価係数」というのが一発でわかりますが、私のように係数をうろ覚えのまま本番に挑んでしまった場合の話をします。
まず問題文では「毎年50万円ずつ10年取り崩す」と書いてあるので、利回りを全無視した場合の計算は、
50万円 × 10年 = 500万円
で必要金額は500万円となりますね。
つまり、利回りを無視(0%で計算)した場合に用いる係数は「10」なので、
運用している分「10よりちょっと少ない数字」が掛けるべき係数なんじゃない?
と推測できます。
そんな偏見を持って表を眺めてみると、
| 係数 | 2% |
| 終価係数 | 1.2190 |
| 現価係数 | 0.8203 |
| 年金終価係数 | 10.9497 |
| 減債基金係数 | 0.0913 |
| 資本回収係数 | 0.1113 |
| 年金現価係数 | 8.9826 |
しっかりそれっぽい数字がありました。
このやり方で無理やり近似値を探し出すというのがこの小技になります。
確かに正直私も当時は係数を暗記していなかったためこのやり方で凌いではきたのですが、この小技の致命的な欠点が1つあります。それが
「利回りが上がるほど正しい係数と乖離していく」
という点です。
例題では2%という低い利回りだったのでさほど問題はありませんでしたし、最近までは超低金利時代のため実際の問題でも著しく乖離するような高利回りの問題は出題されませんでした。
しかしこの先金利が上がっていったりすると問題の利回りも高く設定される可能性もあります。
そうなると「0%計算と近い数字を」という雑なやり方は通用しなくなる可能性も充分にあるんですよね。
なのでこの小技はあくまでも最終手段という程度に認識しておいてください。
以上、使えるんだか使えないんだかよくわからない小技の解説でした。
スポンサーリンク
ライフプランに使う6つの係数のまとめ。
- 係数は判明している金額に掛けるだけで答えが出る便利ツール。
- 係数の選択肢は問題で与えられるので正しく選ぶだけ。
- 「増やす(増えていく)」「貯める(積み立てる)」「使う(取り崩す)」の3動作と絡めて覚えよう。
- 「増やすだけ」は「終価係数」「現価係数」のペア。
- 「増やしながら貯める」は「年金終価係数」「減債基金係数」のペア。
- 「増やしながら取り崩す」は「資本回収係数」「年金現価係数」のペア。
- 一応覚えなくてもギリ導き出せる小技はあるけど覚えたほうが早いよ。
こんなところでしょうか。
繰り返しになりますが、やること自体は掛け算1つなので何も難しくありません。
「正しい係数を選べるかどうか」がこの手の問題の全てと言ってもいいでしょう。
選択に不安があればお金の動きをイメージしてそれっぽい係数を選ぶこともできますので、ぶっちゃけボーナス問題と言ってもいいかもしれません。
次回は具体的なファイナンシャルプランニングの手法について触れていきます。
ぶっちゃけ必要ない金融商品とかも覚えさせられたりしますが割り切ってやっていきましょう。
以上です!