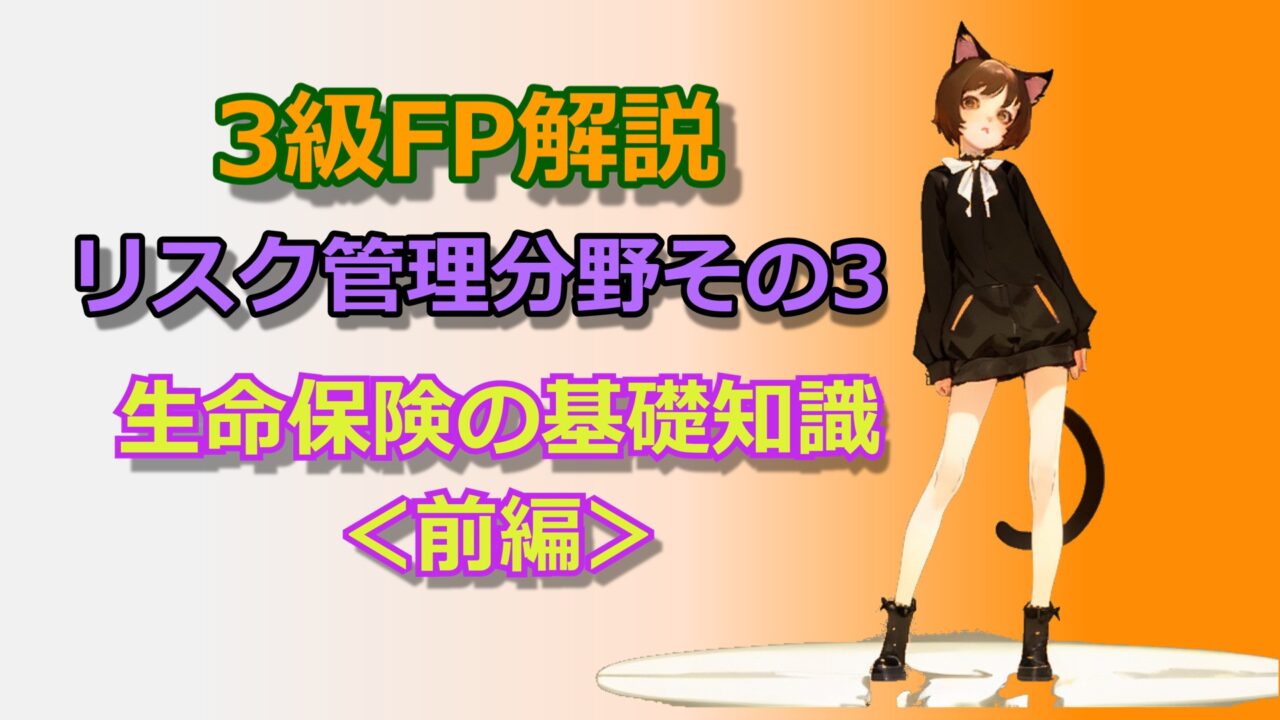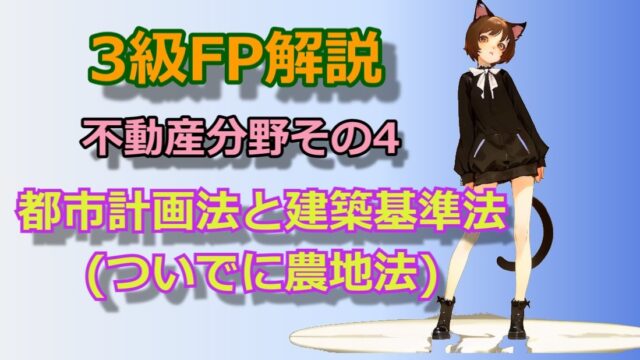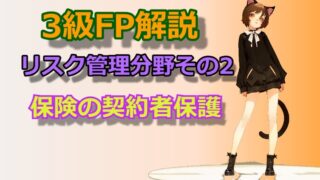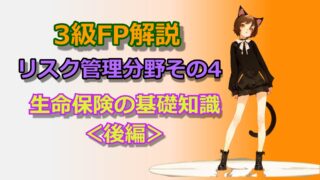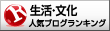今回は3級ファイナンシャル・プランニング技能士試験、リスク管理分野の第3回です。
前回は保険における契約者保護の仕組みについて解説しました。
今回からはいよいよ本番、保険商品の各論に入っていきます。
今回はまず「生命保険」について解説していきますよ。
頑張って2~3回におさめるつもり。
Contents
生命保険の基本的な用語。
まずは解説を行うにあたって覚えておかなければいけない基本的な用語について説明します。
この段階で全て暗記する必要はありませんが、今後の解説の中では当たり前のように出てきたりするので、用語に迷ったらこの項を見返しながら徐々に覚えていってください。
言い換えるより覚えるほうが早いのよ。
僕もそうだった。
保険でよく使われる用語をまとめておきます。
勉強を進める中で覚えていってください。
| 用語 | 内容 |
| 保険契約者 (契約者) |
保険を契約し、実際に保険料を支払う人 |
| 保険者 | 保険会社 |
| 被保険者 | 保険をかけられる人 (この人が亡くなると保険金が下りる) |
| 保険金受取人 (受取人) |
被保険者が亡くなったときに保険金を受け取る人 |
| 保険募集人 | 保険者(保険会社)のために保険契約締結の代理や媒介を行う者 (保険代理店や営業マンなど) |
| 告知 | 被保険者が保険会社に対して契約に影響を及ぼすような重要事実を知らせること 契約前の健康診断などが該当する |
| 保険約款 | 保険会社が契約者に対して事前に渡さなければいけない、保険会社と契約者間の権利義務関係を規定した書類 |
| 契約のしおり | 保険約款の中でも特に重要な事項をわかり易く解説した書類 保険約款と併せて渡す |
| 解約返戻金 | 保険を解約したときに戻るお金 |
| 代理 | 保険募集人が保険会社に代わって契約者と保険契約を締結する行為 |
| 媒介 | 保険会社と契約者の間で仲介や勧誘をする行為 |
| 保険料 | 契約者が保険会社に支払うお金 |
| 保険金 | 被保険者の死亡や満期などのときに保険会社から受取人に支払われるお金 |
| 給付金 | 医療保険などで、被保険者が入院や手術をした際に保険会社から受取人に支払われるお金 |
| 特別勘定 | 契約者が支払った保険料を有価証券で運用すること |
| 主契約 | 生命保険の基本となる部分 |
| 特約 | 主契約に付加して契約するオプション 特約だけでの契約はできない |
| 責任開始日 | 契約した保険の保障が開始される日 |
ここまでの解説の中でもいくつか出てきたものもありますが、ある程度これらの単語の定義は覚えておくといいでしょう。
定義を曖昧なままにしてしまうと混同してわけがわからなくなったりするので、それぞれの単語の意味の違いをイメージできるようにしてください。
スポンサーリンク
生命保険の種類。
生命保険と一口に言っても、契約の内容から大きく分けて3種類の保険が存在します。
その区分として、
- 死亡保険
- 生存保険
- 生死混合保険
がありますのでそれぞれ解説していきますね。
一般的に「生命保険」と聞いて最初にイメージされるのが1番の「死亡保険」です。
これは被保険者が死亡または高度障害になった場合に保険金が下りるタイプの保険です。
掛け捨ての「定期保険」や、貯蓄機能もある「終身保険」などが該当します。
2番の「生存保険」は逆に、一定期間被保険者が生きている場合に保険金が下りるタイプの保険です。
老後のために入る「個人年金保険」や子どもの進学のために使われる「学資保険」などが該当します。
意味ある?
ただしこの手の保険商品自体は個人的にあまり意味はないと思ってる。

そして3番は死亡保険と生存保険を組み合わせた「生死混合保険」です。
死亡したら死亡保険金が出て、一定期間生きていたら満期保険金が下りる「養老保険」などが該当します。
生命保険には3種類あることと、それぞれに該当する保険をざっくり覚えておけばいいかと思います。
保険料算定の方法。
保険に加入するうえで必ずついて回るのが保険料です。
この保険料は保険会社が適当に決めているわけではなく、ある程度の根拠を元に算出しています。
保険料は主に3つの数字(率)から算出されていて、それが
- 予定死亡率
- 予定利率
- 予定事業費率
です。
これらの数字を過去の統計から算出し、その数字を元にして保険料と保険金が釣り合う(ある程度の利益が出る)ように保険料の上下で調整しているわけですね。
それではそれぞれ見ていきましょう。
なかなか縁起でもない「予定死亡率」。
保険会社にとって、保険に加入した人がバタバタと死んでいくと死亡保険の保険金の支払いが増えて大変です。
なので保険会社では人々の属性(性別や年齢など)ごとに「この先何年くらいでどれくらいの割合で死亡していくのか」という統計を取っています。
この数字が「予定死亡率」です。
これだけ聞くとなかなか縁起でもない失礼な数字ではあるのですが、主に人の死亡で支払保険金がかさんでくる保険会社にとってはいちばん大事な数字とも言えます。
例えば男性と女性であれば男性のほうが寿命が短いので予定死亡率は男性のほうが高く出ますので男性のほうが保険料は高い傾向があります。
若い人と老人では若い人のほうがこの先長く生きるでしょうから死亡保険の保険料は若者のほうが安くなる傾向があります。
こんな感じで属性によって契約者が支払う保険料は変わってくるということですね。
生存保険については一旦無視してください。
保険会社は死亡する人が多ければそれだけ多くの保険金を支払わなければいけませんので、その分を受取る保険料でカバーしなければならなくなりますよね。
なので、「予定死亡率が上がれば保険料も上がる」「予定死亡率が下がれば保険料も下がる」というふうに覚えておくといいでしょう。
受け取った保険料をどれだけ増やせるか「予定利率」。
保険会社は、契約者が支払った保険料をボケーっとしてただ持っているわけではなく、主に債券で運用されています。
保険会社が運用してこの先得られるであろう利回りを予測した数字を「予定利率」といいます
主な運用先は債券ですので、国債の利回りなどを参考にして保険の予定利率を決定し、その上下によって保険料の算定結果が変わってくるわけですね。
その運用が儲かればその分を保険金の支払いに充当することができますし、逆に損をしてしまうと保険金支払いに足りない分は新たに徴収する保険料で補填するしかありません。
なので、「予定利率が高くなれば保険料は下がる」「予定利率が低くなれば保険料は上がる」と覚えておきましょう。
運営経費も保険料に含まれるよ「予定事業費率」。
保険会社が事業をやっていくのにも当然経費はかかります。
人件費や家賃、水道光熱費、代理店に支払う手数料などがそうですね。
これらの事業経費がこの先どれくらいかかってくるかを予測した数字を「予定事業費率」といいます。
経費がかさめば保険金の支払いのための資金が足りなくなってしまい、その分は受け取る保険料で補填していくしかありません。
逆に思ったより経費がかからなかったりすると保険金の支払いに余裕が出ますので、(やるかどうかは別として)保険料を引き下げてもやっていけるでしょう。
というわけで、「予定事業費率が高くなると保険料も上がる」「予定事業費率が低くなると保険料も下がる」というふうに覚えておくといいです。
3つ見てきましたが、保険料と同じ動きをするのは「保険会社側の利益になる予定利率」、保険料と逆の動きをするのは「保険会社の損失になる予定死亡率と予定事業費率」という感じですね。
スポンサーリンク
生命保険における保険料の仕組み。
我々契約者が保険会社に支払う保険料は、支払うときには一緒くたにされているのですが、実は保険会社の内部では2つに分けて処理されています。
正直契約者側にしたらどうでもいいことではあるのですが、ここでは保険料の構成について解説しておきますね。
保険料の構成は「純保険料」と「付加保険料」の2つで構成されています。
それぞれ簡単に説明します。
保険金に充当されるのが「純保険料」。
保険会社が集めた保険料のうち、主に保険金の支払いに充当される部分を「純保険料」といいます。
純粋!って感じしますよね。
純保険料は「予定死亡率」や「予定利率」を元に決定されます。
上で述べた「予定死亡率が上がると保険料が上がる」などは「純保険料が上がる」ということになりますね。
そして、純保険料はさらに「死亡保険料」と「生存保険料」に分かれます。
死亡保険の純保険料は死亡保険料、生存保険の保険料は生存保険料といったように、保険会社ではそれぞれを分けて管理・運用して保険金の支払いに備えているわけですね。
保険金には使われない「付加保険料」。
一方、保険金の支払いには基本的に充当されない保険料のことを「付加保険料」といいます。
付加保険料は保険金ではなく、
- 保険会社の維持管理費用(家賃や人件費など)
- 代理店への報酬
- 保険会社の利益
といった形で使われています。
付加保険料は「予定事業費率」を元に算出されています。
「予定事業費率が上がれば保険料が上がる」というのは、結局コストの上昇がそのまま保険料に転嫁されているということですね。
保険会社も営利企業だし保険会社も代理店も付加保険料を多く取れる保険商品を売りたがってるよ。
だからぶっちゃけおすすめしない。
なぜか保険にもある配当金。
保険料についてはここまで説明してきたような要素で決定されます。
しかし、保険料の算出根拠は全て「予定」つまり将来の予測に過ぎないため、実際に運営していった結果とは差額が発生します。
その差額で余ったお金のことを「剰余金」といい、この中の一部を「配当金」という形で契約者に支払っているんですね。
この項ではその辺について説明していきますよ。
剰余金発生の仕組み。
まずは配当金の原資である剰余金がどのように発生するかの仕組みについて説明します。
まあ知っておいて損はないから…。
剰余金は上で述べた通り、
保険会社の収入(保険料など) – 保険会社の支出(事業費用・保険金など)
で算出されます。
この剰余金が出る理由としては、上で述べた
- 予定死亡率
- 予定利率
- 予定事業費率
と現実とのギャップによって生まれます。
保険は上の3つの数字を見込んで(建前上)釣り合うように設計されていますので、その設計との乖離で余ったお金が剰余金ということになりますね。
まず、実際の死亡率が予定死亡率より低かった場合、死亡した人も少なくなって保険金の支払いが減り、結果手元のお金が増えて剰余金が発生します。
こうして手元のお金が予定より増えることを「死差益」といいます。
次に、実際の保険会社の運用利回りが予定利率より高かった場合、運用益が予定より増えますので、これも手元のお金が増えて剰余金が発生します。
このお金の増加は「利差益」といいます。
そして、実際の事業費が予定事業費率よりも低かった場合についても、経費が減っているため手元のお金は増えて剰余金が発生します。
このお金の増加は「費差益」といいます。
その場合は「死差損」「利差損」「費差損」てなるけどぶっちゃけFP試験絡みで見たことない。
差損が出たら内部留保とかの別のところからお金を持ってきて補填するしかないよね。
それぞれの剰余金発生のパターンを表でまとめておきます。
正誤問題とかではやはり逆のことを言って引っ掛けてきたりするのでしっかり覚えましょう。
| 発生原因 | 構図 | 備考 |
| 死差益 | 予定死亡率 > 実際の死亡率 | 保険金の支払が減ってお金が余る |
| 利差益 | 予定利率 < 実際の利回り | 運用で儲かってお金が余る。 |
| 費差益 | 予定事業費率 > 実際の事業費率 | 経費削減で支出が減ってお金が余る。 |
こんな感じで出た剰余金を原資にして配当金が出るという仕組みになっているわけですね。
配当金から見る保険の分類。
ここまであたかも全ての保険で配当金が出るかのように剰余金の仕組みとかを説明しましたが、そもそも保険には配当金が出るものとそうでないものが存在します。
なのでこの項では、配当金の有無から見た保険の分類について少し触れます。
てか君いつから生きてんの?猫又?
まず、どれだけ差益が出ようとも絶対に配当を出さないと最初から決めている保険のことを「無配当保険」といいます。
で、何らかの形で配当が出る保険のことを「有配当保険」というのですが、この有配当保険は配当原資の違いによって2つに分かれます。
まず、上で述べた「死差益」「利差益」「費差益」のどれで剰余金が発生しても配当を出す保険のことを(狭義の)「有配当保険」または「三利源配当型保険」と呼びます。
わざわざ小難しい名前つけなくても…。
そして「利差益」から発生した剰余金のみを原資として配当金が支払われる保険のことを「準有配当保険」または「利差配当付保険」といいます。
要は「資金の運用が思ったより儲かったときだけ配当出しますよ」という保険で、死差益や費差益で剰余金が出た場合には契約者に還元されないということになります。
最後が「無配当保険」で、こちらはいかなる差益が出た場合でも契約者に配当は出ない保険です。
ところがそうはいかないのが保険という金融商品で、一見条件が良さそうな部分がある保険というのは、契約者が支払う保険料が割高なるように設計されています。
なのでこの分類だけを考えた場合、一概にどの保険がお得というのは判断できないということになります。
どうせ配当が出たって保険会社に抜かれるんですから保険の配当なんか当てにしちゃダメです。
一応これらの保険を保険料の高い順に並べると、
- 有配当保険(三利源配当型保険)
- 準有配当保険(利差配当付保険)
- 無配当保険
となります。
FP試験ではこの辺も覚える範囲には入るんですが、実生活で保険に加入する場合は高配当を謳った保険は必ずしもお得ではないですし、保険の配当なんて知れてますから正直重視するようなことではないことこそ覚えておいたほうがいいでしょう。
スポンサーリンク
保険契約の流れ。
ここからは実際に保険契約を締結するにあたってどういう流れで契約が発効するのかということについて解説していきます。
大きな流れとしては、
- 申し込み
- 告知
- 保険料払込
- 保険契約の発効
といった感じになり、保険契約の発効(責任開始日)は上記の1~3が全て済んだ日となります。
このうちどれが欠けても保険契約は発効せず、その間に保険金支払い事由の事故が起こっても保険金が支払われないことになります。
この流れについてそれぞれ説明しますね。
契約者が負う「告知義務」について。
契約者が保険に加入したいと思っても、ただ申込書に記入するだけで保険に入れるわけではありません。
保険加入に際しては契約者側にもある程度の義務が課せられます。
その1つが「告知義務」で、契約者及び被保険者は保険会社が定めた質問に答える義務があります。
というのも、契約者が加入したいと思っても、被保険者が予定死亡利率からかけ離れた病気をすでに患っていたりすると死差益(死差損)に直結するため加入を断ったり保険料が変わってきたりしてしまうため、契約者の意思だけでは契約を成立させることができないようになっているんですね。
そのへんの問題をクリアするために、保険会社は契約者や被保険者に対して健康状態等に関する告知を受ける権利を持っています。
厳密には保険会社と診察医がその権利を持っており、生命保険募集人にはその権利はありません。
なので営業の人に口頭で告知しても無効となり、ちゃんと診察医の診断を受けるか書面を保険会社本体に提出して初めて告知義務が果たされることになります。
保険商品によって内容が変わりますが、いくつかの質問が書かれた書類の提出で済む場合もあれば、健康診断などの診断書の提出を求められることもあります。
契約者や被保険者が虚偽の告知を行った(告知義務違反)場合、保険料の支払いが済んでいたとしても保険会社はその契約を解除することができます。
なお、契約者が告知義務違反をした場合においても、保険会社が契約解除ができる期間は限られており、
- 契約解除の原因があることを知ったとき(告知義務違反を知ったとき)から解除権を行使せずに1ヶ月が経過したとき。
- 保険契約の締結から5年が経過したとき
に保険会社の解除権が消滅する決まりになっています。
ちなみに保険募集人が虚偽の告知を勧めた場合や告知義務違反を知っていて黙っていた場合にあとから保険会社にバレた場合でも保険契約を解除することができます。
保険料の払込について。
まず、一口に保険料の払込といっても支払い方には
- 月払い
- 半年払い
- 年払い
- 一時払い
などいくつかの方法があります。
月払いはよくある毎月支払うタイプの一般的な支払い方ですね。
半年払い、年払いについては半年または1年分をまとめて支払う方法で、一時払いは保険期間中の総保険料を一括で支払うブルジョアな支払い方法です。
基本的に前払いする期間が長いほど保険会社が運用できる期間が長くなるため、その分保険料が割安になる傾向があります。
なので保険料総額の高さを並べると、
月払い > 半年払い > 年払い > 一時払い
となりますね。
なお、保険料の支払いが家計の事情などで支払えない、間に合わないといったこともあるかも知れません。
その場合は即座に契約が消滅するわけではなく、「猶予期間」という救済措置が定められています。
猶予期間は、
- 月払いの場合は「払込期月の翌月いっぱい」
- 半年払・年払いの場合は「払込期月の翌月初日から翌々月の契約応当日まで」
となっています。
例えば1月10日に契約、そのときに保険料を支払う決まりだったとします。
月払いの場合は翌月いっぱいですので、2月1日から2月28日までが猶予期間となり、その間に保険料を支払えば失効せずに済みます。
半年払いや年払いの場合は、翌月初である2月1日から翌々月である3月の契約応当日にあたる10日までが猶予期間となります。
この期間をすぎると保険契約は失効してしまい、その後に何かあっても保険金を受け取ることもできなくなります。
ちなみに一時払いは保険期間中の保険料をすでに支払っている状態ですのでもちろん猶予期間もなく契約が失効することもありません。
万一猶予期間中に保険金支払い事由(被保険者の死亡など)が発生した場合は保険金はちゃんと支払われますが、失効してしまった場合はもちろん保険金は支払われません。
後で困らないように支払いはちゃんとしましょう。
また、失効中は保険金の支払いはありませんが、一旦失効した保険契約を一定条件のもとで「復活」させることも可能です。
保険料払込に関する制度いろいろ。
ライフスタイルの変化で必要な保証が変わったり、収入減などにより保険料の支払いがきつくなったりしたときのために、保険にはいくつか救済(?)制度がありますのでそのへんについても触れていきますね。
保険の乗り換えのときに使える「契約転換制度」。
こちらはライフスタイルの変化によって必要な保証が変わった場合などに利用できる制度です。
具体的には、従前の保険で支払った保険料のうちの積立部分を、乗り換えたあとの保険にかかる保険料として充当することで新しい保険の保険料を少し安くできる仕組みで「契約転換制度」といいます。
これだけ聞くとなんてお得な制度かと思ってしまいそうですが、いくつか注意点がありますので覚えておいてください。
- 乗り換えたときの年齢や属性で保険料が再計算される。
- 新たに告知や医師の診断が必要になる。
- 旧保険が掛け捨て(定期保険など)の保険だとそもそも使えない。
まず保険料の再計算についてですが、基本的に保険料は若ければ若いほど安くなります。
旧保険を契約したときより若くなっていることはありえないので、基本的には保険料率は旧保険よりも新保険のほうが高くなってしまう点には注意が必要です。
旧保険の積立部分を新保険の保険料に充てているため保険料自体は安くはなるでしょうが、単体で見ると当初より割高な保険料を支払い続けることになる点は覚えておいてください。
そしてこの制度では新しく保険に加入するのと一緒ですので、保険を乗り換える際には告知や医師の診断は当然必要になってきます。
診断の結果、新たに病気が見つかった場合などは最悪加入を断られてしまう可能性もありますのでご注意ください。
最後のはそのまんまで、もともと積立部分のみが新保険の保険料に充当されますので、積立部分の存在しない掛け捨ての定期保険などから乗り換えたところで充当できる金額はゼロ円となります。
なのでこの制度は積立部分のある保険から乗り換える場合にのみ使える制度となっています。
実生活で必要な制度とも思えない。試験だけのために覚えとく知識。
保険料の「減額」。
次は「今の保険料きついけど少し安くなればなんとか払えるのにな…。」くらいに保険料の支払いに困っている人のための制度です。
具体的には、現在入っている保険の保障額(保険金)を減らして支払保険料も減らす「減額」というやり方です。
減額を行った場合、削減した部分は解約扱いとなります。
なので解約返戻金がある場合は減額分の返戻金を受け取ることができます。
こっちはまあいろいろロスの多い転換制度よりも現実的な選択肢ですね。
もっと支払いがきついときには「払済保険」や「延長保険」への変更。
「いやもうこの先支払自体がキッツいわ!」という場合には、以後の保険料支払が必要なくなるようにできる制度も存在します。
まず「払済保険」についてですが、こちらは現在加入している保険の解約返戻金を原資として一時払の保険と同様の扱いをすることで以後の支払がなくなります。
ただし、今後保険期間満了まで保険料を支払い続ける保険と、今まで貯まった解約返戻金で支払いが済んでしまう保険とでは保障額が同じになるわけはありませんよね。
なので払済保険化を行うと必ず保障額(受取保険金の金額)が著しく下がるということは覚えておいてください。
「延長保険」については、原資が解約返戻金となるのは払済保険と同様ですが、こちらは元の保険から「一時払の定期保険」と同等の保険に変更されます。
つまり以後の保険は解約返戻金の発生しない掛け捨ての保険に変身してしまうわけですね。
払済保険は保険金がゴリゴリに削られてしまいましたが、延長保険については保険金は基本的に減りません。
ただし、解約返戻金相当額で同じ保険金額を賄える定期保険への転換ですので、保険期間はその解約返戻金で賄える期間に限られます。
つまり、保険金を削らない代わりに保険期間をゴリゴリ削るということになりますね。
延長と聞くと保険期間が伸びそうなイメージを持ってしまいそうですが、この「延長」というのは「もう払えないから終わる保険だけど解約返戻金の分だけ延長してやってもいいぜ!」の延長だと思っておいてください。
保険金をそのままにしたければ延長保険」という二択ですね。
ちなみに元の保険に特約などをつけていた場合、それらは全て消滅します。
保険内容は変えたくないけどお金がない人の最終手段「契約者貸付制度」。
今の保険の保障内容は絶対変えたくないけどお金がなくて保険料を支払えない、という人向けの最後の手段とも言える制度が「契約者貸付制度」というものです。
簡単に言ってしまえば要は「借金」のことです。
これはもちろん解約返戻金のある保険でのみ使える制度で、その解約返戻金の金額を限度として保険会社が契約者に対し金銭の貸付を行えるというものです。
中身は普通の借金ですので当然利息はかかります。
慢性的にお金がない状況下において利用するのはおすすめしません。
そして、契約者貸付制度を利用して、引き落とせなかった保険料を解約返戻金の枠内から自動的に貸し付けて保険料に充当するという鬼のような制度を「自動振替貸付制度」と言います。
この2つは本当に最後の手段というか、保険会社が契約者を囲い込むためにあるだけのシステムですので、試験のために覚える必要はあっても契約者にとって有利になるような制度では全くありません。
保険料がしんどくなったらまずは「保障の見直し」ということは忘れないようにして下さい。
スポンサーリンク
生命保険の必要保障額を計算する。
生命保険、中でも死亡保険は被保険者が死亡した場合に遺族(主に独立していない子ども)の生活を支えるために利用されます。
とは言っても適当に見積もりすぎて少なければ遺族が路頭に迷いますし、多すぎれば保険料を無駄に支払ってしまうことになります。
なのでこの項では、必要な保障額をざっくりと計算する方法について説明していきます。
この金額を計算式で雑に表すと、
必要保障額 =これからかかる支出 – (今ある資産 + この先の収入)
となります。まあ当たり前ですね。
もちろんこの先の収入や支出は推測による見積もりとなりますので、ライフステージや物価に変化があればその都度見直していく必要が出てきます。
それではこの式の中身についてそれぞれ見ていきましょう。
ただし前提として、「世帯の中で収入を持ってくるのは被保険者、配偶者と独立前の子どもはその後も働かない」という古い価値観によって成り立つものと思ってください。
実際に共働き家庭でのシミュレーションをする場合は遺族配偶者の収入も加味して計算する必要があります。
まず「この先の支出」についてです。
支出のメインとなるのはまず「この先の遺族の生活費」ですよね。
生活費に関しては子どもの独立前と独立後で金額が結構変わってきますので、そこを分岐点として「末子独立までの生活費」と「末子独立後の配偶者生活費」に分けて考えます。
問題などでは、
- 被保険者死亡前の生活費は〇〇円
- 末子独立までの生活費は死亡前の〇〇%
- 末子独立後の配偶者の生活費は死亡前の〇〇%
といった数字と、配偶者の家庭の余命などが与えられますのでそれらを元にコツコツ計算していきます。
そうして算出した生活費に「その他の必要資金」がオンされます。
その内容は、
- 被保険者の葬式代
- この先の住居費(賃貸なら家賃、持ち家なら修繕費用など)
- 進学などによるまとまった教育費
- さらに何かあったときのための予備費
などが該当します。
やはり問題ではこれらの数字が与えられますのでこちらもコツコツ足し合わせていってください。
団信(団体信用生命保険)
住宅ローンを組む際に大体の人が加入させられる生命保険で、住宅ローン完済前に契約者が死亡した場合、保険によって住宅ローンの残りがチャラになるという気の利いた保険商品です。
持ち家の場合は「団信に加入している」といった旨が条件として記載されていることがあり、その場合は死亡後の住宅ローン返済金額は計算から除外します。
賃貸であれば団信の記載はされませんので家賃をそのまま支出に加算することになります。
支出の概算が出たら次はそこから引く部分です。
「今ある資産」については基本的には現金を初めとする流動資産だと思っておいてください。
これに不動産などを含めてしまうと被保険者の死亡後に遺族が路頭に迷ってしまうことになります。
「この先の収入」については、「遺族年金」や「被保険者の死亡退職金」などが含まれます。
共働き家庭の場合はここに「遺族配偶者の収入」を加えます。
こうして出た金額を、先ほど出した支出から差し引いて必要保障額を求めるわけですね。
というわけで例題で計算してみましょう。
ちなみにこのあたりで12,000字を超えています。
例題
Aさんは配偶者と子ども1人の3人家族だったが今年Aさんが亡くなった場合に備えて保険金がいくらの死亡保険に加入すべきか。
ただし諸条件は下記のとおりとする。
- 現在の生活費は月額平均20万円。
- 配偶者と子どもの生活費は現在の60%とする。
- 子ども独立後の配偶者の生活費はA現在の40%とする。
- 子どもの独立は10年後、配偶者の余命は現在から40年後とする。
- 葬儀費用は200万円、進学費用を含む教育費は800万円とする。
- Aさん死亡時点での住宅ローン残債は2300万円とする。
- Aさんは住宅ローンの借入時に団体信用生命保険に加入している。
- 持ち家の修繕費、その他の予備費を併せて200万円を見積もっている。
- Aさんの死亡退職金は400万円とする。
- Aさん世帯の保有する金融資産は500万円。
- 今後配偶者が受け取る遺族年金等の公的年金は合計3000万円とする。
- 配偶者は今後も頑なに働かないものとする。
まずは支出から見ていきましょう。
条件の中で支出に該当するものは、
- 子ども独立前の生活費10年分
- 独立後の生活費30年分(40年-10年)
- 葬儀費用 200万円
- 教育費 800万円
- 修繕費、予備費 200万円
です。
住宅ローンの残債は団信でチャラになりますので2300万円は無視します。
他のを足し合わせて今後の支出を計算することになりますが、生活費は計算が必要ですね。
現在の生活費は毎月20万円、Aさん死亡後のさん死亡から子どもの独立までは60%とのことなので、Aさん死亡後の2人の生活費は
20万円 × 60% × 12ヶ月 × 10年 = 1440万円
となります。
子ども独立後から配偶者の余命までは40-10で30年、20万円の40%とのことなので、
20万円 × 40% × 12ヶ月 × 30年 = 2880万円
となりますね。
これらにその他の必要資金を足し合わせると、
1440万円+2880万円+200万円+800万円+200万円=5520万円
これがAさん死亡後に必要となる金額です。
次に収入について見てみると、
- 死亡退職金 400万円
- 金融資産 500万円
- 公的年金 3000万円
となっています。
配偶者は今後も働かないということなので収入はこれだけになりますね。
合計すると
400万円+500万円+3000万円 = 3900万円
となり、この数字を先ほどの支出から差し引きます。
5520万円 – 3900万円 = 1620万円
こんな感じで必要保障額は1620万円と算出できます。
多分実際は年金そんなに出ないしね。
とかく死んだ後のことだと大きく見積もりがちだから、ざっくりでいいから計算してみるのは一度やってみるといいですよ。
スポンサーリンク
生命保険商品についてのまとめ。
- 似た用語はちゃんと区別して覚えよう(「保険金」と「保険料」など)。
- 生命保険は「何について保障されるのか」で3種類に分類される。
- 保険料は「予定死亡率」「予定利率」「予定事業費率」の3つの数字によって算出される。
- 保険金等に回されるのは「純保険料」のみで、「付加保険料」は保険会社の経費などに回される。
- なので付加保険料が発生する要素の多い保険は保険料が割高になる傾向がある。
- 純保険料は予定死亡率と予定利率が影響し、付加保険料は予定事業費率が影響する。それぞれの関係を押さえておこう。
- それぞれの「率」で浮いた分を「剰余金」として「配当金」をだす保険もある。
- 剰余金の発生原因をしっかり押さえておこう。
- 配当の有無で分類されることもあるのでこの辺も覚えておこう。
- 契約者や被保険者にも「告知義務」という縛りがある。ここで嘘ついちゃダメ!
- 告知義務違反について保険募集人が唆しても保険会社の瑕疵にならない点には注意。
- 保険料はまとめて払うほど運用期間が長くなるためお得。
- 保険料の支払いがキツいときにはいくつかの救済措置があるが、その分デメリットもある。
- 必要保障額の計算は試験に関係なく有用なので一度やってみるのがおすすめ。
こんな感じでしょうか。
これまだ続くのか?
どうもFPというのは保険業界とのしがらみが強いのか、他の分野に比べて物量が多い気がします。
そもそも保険だけで1分野、他の金融商品をまとめて1分野という時点でおかしい気もしますよね。
ただ、この辺をどうこう言っても始まりませんし、保険のことについて知っておくこと自体は必要ですのでなんとかかんとか頑張っていきましょう。
次回は生命保険商品にどんなものがあるかというのを中心に解説していきます。
今回ほどは長くならないと思いますのでお付き合いいただければ幸いでございますよ。
以上です!