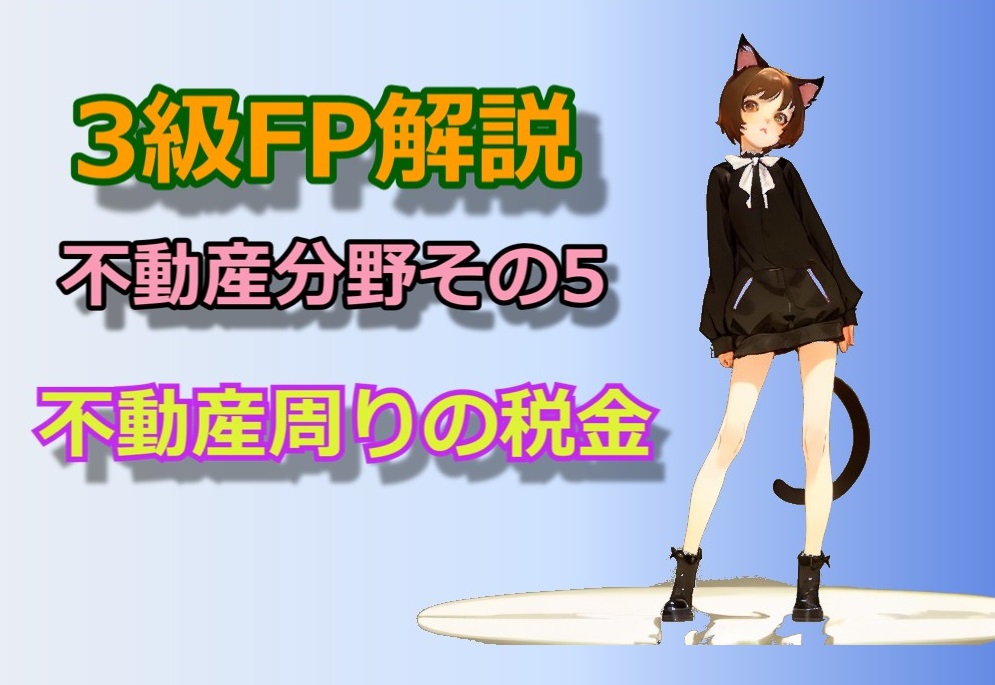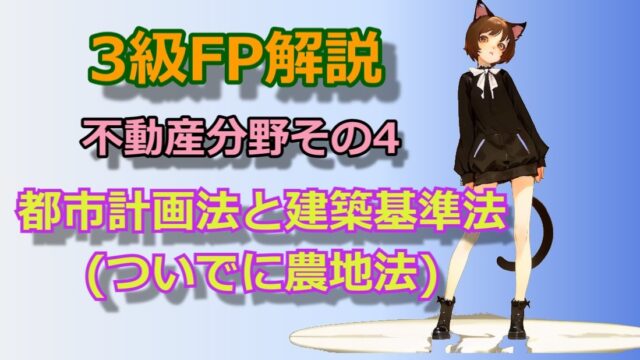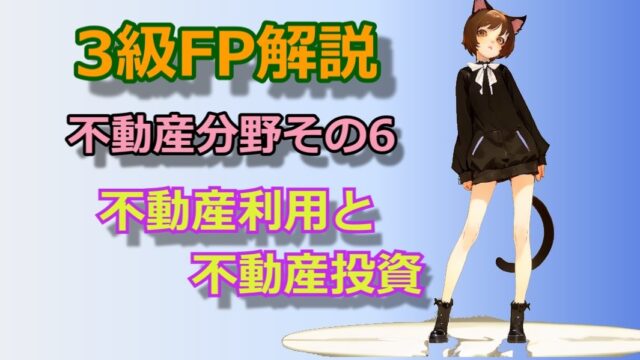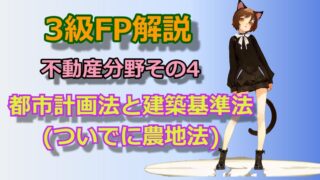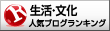今回はFP3級、不動産分野の第5回です。
前回は不動産絡みの法律という非常にとっつきにくい内容でしたが、今回はそれに輪をかけてとっつきにくい税金のお話です。
学ぶのはしんどいわ実際にやっても税金取られてしんどいわとかなりモチベーションの下がる分野ですがめげずに頑張っていきましょう。
Contents
不動産について回る税金4パターン。
不動産にはどうやっても税金がついて回ります。
具体的には以下の4パターンで税金がかかってきますのでイメージを把握しておいてください。
- 取得した時…不動産取得税、登録免許税、印紙税、消費税
- 持っている間全て…固定資産税、都市計画税
- 賃貸している時…所得税(不動産所得)、住民税
- 売った時…所得税(譲渡所得)、住民税
普通の資産であれば持っているだけであれば税金がかからないので3パターンですが、不動産は通常の資産よりも1種類多いのは覚えておいてください。
ではそれぞれ見ていきましょう。
不動産を取得した時にかかる税金。
まずは不動産を買ったりもらったりした時にかかる税金です。
種類としては、
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 印紙税
- 消費税
の4つがあります。
ではそれぞれ解説していきますよ。
1.不動産取得税
「不動産取得税」はその名の通り、「不動産を取得した時にかかる税金」です。
また、建物の増改築のときなんかにも課せられます。
基本的には対価の有無にかかわらず、買おうがもらおうが取られてしまうのですが、「相続」や「法人の合併」によって取得した場合は不動産取得税はかからないことになっています。
不動産取得税は
- 地方税の一部で
- 都道府県が
- 不動産を取得した人に対して
- 固定資産税評価額を元に
- 3%
課税されます。
不動産取得税の特例
本来の税率は4%とされていますが、2027年3月31日までに土地や住宅を取得した場合に限り特例として3%の税率が適用されます。
ちなみに、固定資産税評価額を元に算出した不動産の価格のことを「課税標準」と呼びます。
課税標準とだけ聞いてもあまりピンときませんが、問題文などで当たり前のように使ってくるので不動産価格のことだというのは頭に入れておくといいでしょう。
不動産取得税にかかる課税標準の特例。
上述したように不動産は何かと税がついて回るものです。
しかし不動産には「住むところ」という生活に必須な要素と密接に結びついている側面もあります。
なので、土地や建物においては「住むところ」として扱う場合に限って税金を軽減する仕組みが存在するんですね。
詳しく見ていきましょう。
まず土地についてですが、「宅地の場合に限り課税標準を1/2にして不動産取得税を計算する」という特例があります。
例えば、固定資産税評価額が2000万円の住宅の場合、特例がなければ2000万円丸ごとに税率3%をかけて60万円が不動産取得税として課税されるはずです。
しかしこの特例によって計算根拠となる金額が半分にされるため、不動産取得税は
2000万円 × 1/2 × 3% = 30万円
と半分になるというからくりです。
一方の建物については別のルールがあり、「一定の新築住宅については課税標準から最大1200万円を控除した金額で不動産取得税を計算する」ことになっています。
「最大1200万円」というのは「マイナスにはならない」という意味ですので、1200万円以内の住宅であれば不動産取得税がかからないということになりますね。
ちなみに「一定の新築住宅」は「自分で住む家であること」、「床面積50㎡以上240㎡以下」などの条件を満たしたものが該当します。
また、1200万円という金額は1997年4月1日以降に建てられた住宅においての金額で、それ以前に建てられたものについては基本的に古くなればなるほど控除額は減っていきます。
中古住宅を取得した場合は、その住宅が新築で建てられたときの控除額が適用されます。
2.登録免許税
次に「登録免許税」ですが、こちらは不動産を登記するときにかかる税金です。
取得とは別に更に課税されるのは納得いかない気もしますが、不動産は国や自治体にとって財源の宝庫だというのがよくわかりますね。
登録免許税は、
- 国税の一部で
- 国が
- 不動産の登記を行う人に対して
- 固定資産税評価額を元に
課税する税金です。
ただし、抵当権設定登記だけは債権の金額が基準になります。
あと、納税義務者については建前上は不動産の売主と買主が連帯してなることになっていますが、ほとんどの場合は契約書に「買主が負担する」と記されて買主が負担するのが慣例になっています。
不動産の登記の種類。
不動産にかかる登記に主に3種類あります。
それが、
- 所有権保存登記 … 新築の建物を購入したり建てたときに行う。
- 所有権移転登記 … 不動産を売買したり相続したときに行う。
- 抵当権設定登記 … 抵当権を設定したときに行う。
といった感じになります。
簡単に言うと保存登記は新規で設定する登記で、移転登記は中古物件の移動記録のようなイメージですね。
なので抵当権自体の説明を少し。
「抵当権」は、その不動産を購入した人が借り入れを行った場合に貸し付けた金融機関が設定します。
その借り入れについての返済が滞ったときに、その不動産を債権者が処分できる権利のことを抵当権というわけですね。
住宅ローンを借りたらだいたい銀行の抵当権がついてきますよ。
まあ担保みたいなもんですね。
あと当然ですが、土地には新築はないため基本的に所有権保存登記を行うことはありません。
登録免許税の税率。特例もあるよ!
上の概要では税率について触れませんでしたが、それは「内容によって税率がバラバラすぎる」からです。
なので一部ではありますが下の表にまとめておきます。
| 一般 (土地・事業用建物) |
特例 (住宅) |
||
| 所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% | |
| 所有権 移転登記 |
売買 | 2%(※) | 0.3% |
| 相続 | 0.4% | – | |
| 贈与 | 2% | – | |
| 抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% | |
※2025年3月31日までに登記した場合は0.15%
で、上の表を見るとわかる通り、登録免許税にも特例が存在します。
この特例は、対象不動産が住宅の場合に原則の登録免許税率よりも低い税率が適用されるというものです。
なお、相続や贈与で住宅を取得した場合は登録免許税はかかりません。
3.消費税
消費税に関してはまあみなさんがご存知の消費税のことです。
住宅購入時などでは税込の価格で売価が設定されていることがほとんどなので実感はないかもしれませんが、しっかり消費税は取られています。
なお不動産に関しては、建物に対してのみ消費税が課税され、土地については非課税となります。
まあそりゃそうだよね。
建物については、個人間で住宅を売買した場合は消費税はかかりませんが、事業用建物だと消費税がかかります。
不動産業者から購入した場合は居住用でも事業用でも消費税は課税されます。
ついでに取得時以外の消費税についても少し説明しておきます。
土地の貸付に関しては、1ヶ月未満の短期貸付に限り課税となりますが、それ以外は居住用でも事業用でも消費税は非課税となります。
建物の貸付については、居住用であれば非課税、事業用は課税となります。
ややこしいですがしっかり分けて覚えておきましょう。
消費税に関してはこんな感じです。
4.印紙税
もともと印紙税は契約書などの文書を作成したときにかかる税です。
具体的には郵便局などで収入印紙を購入、契約書に定められた金額分の印紙を貼付し、それに契約当事者の消印を押すことで納税義務が果たされます。
納税義務者は契約当事者両方となり、不動産取得時で言えば売主と買主の両方が印紙を貼って消印を押す必要があります。
印紙を貼らなかったり消印を忘れてしまった場合は義務を果たしていないとみなされ、過怠税(追徴課税みたいなもの)が課せられますので注意が必要です。
基本的に不動産の取引は書類ありきで進められることが普通なのでそれに伴い印紙税もついて回るものなのですが、こちらも非課税の契約がありますのでついでに覚えておきましょう。
具体的には、「建物の賃貸借契約書」、「不動産の媒介契約書」、「国や自治体が作成した文書」に関しては非課税になります。
スポンサーリンク
不動産を保有している間にずっとかかる税金「固定資産税」と「都市計画税」。
不動産に関しては、持っているだけで毎年課税される悪魔のような税金である「固定資産税」と「都市計画税」があります。
これは不動産を所有している限り延々と取られ続ける逃れようのない税金です。
順番に説明していきますね。
1.固定資産税
固定資産税は、
- 地方税の一部で、
- その不動産がある市町村(東京23区の場合は東京都)が、
- 毎年1月1日に所有している人に対し、
- 固定資産税評価額を元に
課される税金です。
要は固定資産税相当額を売値に上乗せされちゃう。
固定資産税は「課税標準 × 税率」で計算します。
一般的に税率は「1.4%」とされていますが、市町村の裁量で税率を決めることができる点には注意が必要です。
固定資産税にもある減額特例。
不動産取得税や登録免許税がそうであったように、固定資産税も住居絡みでの特例がありますので見ていきましょう。
まず土地(宅地)についての特例が2種類あります。
「小規模住宅用地」とされる200㎡以下の部分については、
課税標準 × 1/6
に税率をかけて税額を算出します。
そして「一般住宅用地」とされる200㎡超の部分については
課税標準 × 1/3
に税率をかけて税額を算出します。
例えば、1㎡あたりの固定資産税評価額が30万円、宅地面積が240㎡だった場合で計算してみましょう。
特例適用前であれば、
30万円 × 240㎡ ✕ 1.4% = 1,080,000円
と、とんでもない金額になってしまいますが、特例が適用されると、
(200㎡以下の部分)
30万円 × 200㎡ × 1/6 × 1.4% = 140,000円
(200㎡超の部分)
30万円 × 40㎡ × 1/3 × 1.4% = 56,000円
合計 196,000円
となり、かなりお安くなりますね。
宅地の面積が200㎡を超えたら丸ごと1/3にされるわけではないのでそこはご注意くださいね。
とりあえず住宅を建てていることで固定資産税がかなり安くなることはおわかりいただけたかと思います。
次に建物の方の特例です。
こちらは「新築住宅の税額軽減特例」と呼ばれ、
- 一定の要件を満たした新築住宅が
- 3年間または5年間、
- 床面積120㎡までの部分について
- 税額が1/2
に軽減される、というものです。
んで戸建の場合は3年、マンションは5年って感じで分かれてる。
まあ細かくは覚えなくていいけど。
土地と建物それぞれで特例の内容が異なりますので、ごっちゃにならないようにしっかり分けて覚えておきましょうね。
2.都市計画税。
「都市計画税」は、市街化区域内にある土地や建物を持っている人に対してかけられる税金です。
なので、都市部に土地家屋を持つ人は固定資産税と都市計画税をダブルで支払わされることになります。
その内容は、
- 地方税の一部で、
- 不動産が存在する市町村(東京23区は都)が
- 不動産の所有者に対して
- 固定資産税評価額をもとに
- 最高0.3%
課せられるというものです。
「最高0.3%」という数字は市町村がその範囲内で設定することができます。
やっぱりあった特例。
察しのいい方はおわかりかと思いますが、やはり都市計画税にも特例があります。
都市計画税の特例は固定資産税とは違って土地だけに特例があります。
土地の要件はやはり「宅地」であることで、ここは固定資産税のそれと同様、200㎡を基準に減額率が変わってきます。
まずは「小規模住宅用地の特例」として、200㎡以下の部分に対しては
「課税標準に1/3をかけた価格」に税率をかけて税額を算出します。
そして200㎡超の部分に関しては「一般住宅用地の特例」として、「課税標準に2/3をかけた価格」に税率をかけて税額を算出します。
都市計画税は「1/3、2/3」
と覚えておきましょう。
不動産を持っているだけでかかる理不尽な税金についてはこんな感じです。
スポンサーリンク
不動産を賃貸したときにかかる税金「所得税(不動産所得)」。
不動産を有償で貸し出したときに受け取る家賃や地代については、「不動産所得にかかる所得税」として課税されます。
詳しい内容については以前に書いたタックス分野の記事とまるっきり同じですので、ここでは要点だけおさらいしておきましょう。
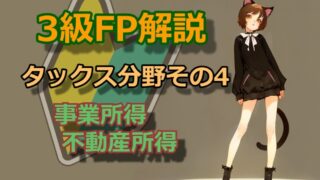
不動産所得の要点は下記の通り。
- 「不動産所得」は不動産を賃貸に出したときに得た賃料などの収入から、それにかかる経費を差し引いた所得のことです。
- 不動産所得は、給与所得や事業所得などの所得と合算した所得に対して税金がかかる「総合課税」となっています。
- 税率は、所得が大きくなるほど高くなる「累進課税」となっています。
| 収入になるもの |
|
| 収入になりそうでならないもの |
※ただし、特約などによって敷金や保証金を返還しないと定めているものに関しては収入となる。 |
| 経費になるもの |
|
| 経費にしたいけどできないもの |
|
- 不動産所得は「青色申告」が可能で、小規模の場合は10万円、5棟10室以上の事業的規模の場合は最大65万円の「青色申告特別控除」を受けられます。
- 不動産所得で赤字が出た場合、基本的に他の黒字所得との「損益通算」が可能ですが、その赤字額に「土地購入のための借入金利子」を含めることはできません。
超ざっくり書きましたが不動産所得にかかかる所得税に関してはこんな感じです。
詳細については上のリンクから不動産所得の記事をご参照いただければと思いますよ。
スポンサーリンク
不動産を売却したときにかかる税「所得税(譲渡所得)」。
最後に、不動産を手放したときにかかる税金についてです。
ここでかかる税金は「譲渡所得にかかる所得税」となっていますので、不動産を手放して損失が出た場合は税金はかからないことになっています。
こちらもタックス分野の記事である程度説明していますので、概要については下の記事をご参照ください。
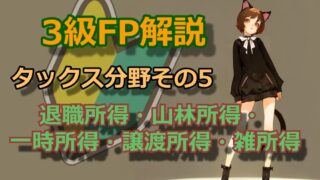
不動産譲渡にかかる譲渡所得についての要点は下記の通りです。
- 譲渡所得は「売却金額 ‐ (取得費+譲渡費用)」で出た金額に税率をかけて算出します。
- 税率はちょっと厄介で、取得した年から売却年の1月1日時点で保有期間が5年以下か5年超かで扱いが変わります。
5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年超だと「長期譲渡所得」という扱いになります。 - 不動産の譲渡所得は他の所得と合算しない「分離課税」となっていますので、特別控除がない限り、所得に直接税率をかけて税額を算出します。
- 税率は、短期譲渡所得の場合は39.63%(所得税30%、住民税9%、復興税0.63%)、長期譲渡所得の場合はちょっとお安くなって20.315%(所得税15%、住民税5%、復興税0.315%)となっています。
- 問題では復興税は考慮しないことが多いので「短期39%」「長期20%」という認識で構いません。
そして、不動産分野の中で紛れて出てきやすい項目がいくつかあるので、一応タックス分野でも触れたところですが改めて詳しく書いておきます。
いくらで買ったのかわからない場合の「概算取得費」。
不動産、特に土地は先祖代々から受け継がれていたりして取得費がわからないケースがよくあります。
そういう場合は、「概算取得費」を取得費として計上できるという特例です。
この概算取得費は、
- 売却金額 × 5%
で計算します。
例えば、
- 売却金額 1000万円
- 取得費 不明
- 譲渡費用 30万円
の場合、取得費が不明なので5%として計算しますので譲渡所得金額は
売却金額1000万円 – 概算取得費50万円(1000万円×5%) – 譲渡費用30万円 = 920万円
となり、税額については取得価額がわからないときはたいてい長期となるので、復興税を除く税額は
920万円 × 20% = 184万円
ということになりますね。
ちなみに取得費がわかっている場合でも、概算取得費である5%よりも安い場合は5%の概算取得費を選んで計算してもOKです。
住宅絡みにはやっぱりある「居住用財産にかかる3000万円の特別控除」。
固定資産税などであった住宅の特例に似たようなものですが、譲渡所得に関しても特例が存在します。
それが「居住用財産にかかる3000万円の特別控除」です。
簡単に言うと、「マイホームやその土地を売って利益が出ても3000万円までは税金かけないようにしてやるぜ!」というシステムですね。
計算した居住用財産の譲渡益が3000万円以下の場合は、課税される譲渡所得がゼロになります。
この場合は短期であっても長期であっても元がゼロですから税額もゼロとなります。
一方、譲渡益が3000万円を超えた場合は、譲渡益から3000万円を控除してはみ出た部分に、短期なら39.63%、長期なら20.315%をかけて税額が算出されるということになります。
不動産の譲渡所得にかかる特別控除は実はいくつもあるのですが、普通の人には馴染みのないものが多いので3級では居住用財産の3000万円しか扱いません。
その他の特別控除に興味のある方は下のリンクからどうぞ。
まだあるの!?「居住用財産の軽減税率の特例」と「特定居住用財産の買い替えの特例」。
ここはタックス分野で触れなかった項目ですが、実は居住用財産を譲渡した場合にはさらに特例が設けられています。
先程、売却した年の1月1日時点で5年超の場合は長期譲渡所得として税率が下がると書きましたが、居住用財産に限り売却年の1月1日時点で10年超の場合にはさらなる特例措置があります。
具体的には以下の2つ。
- 譲渡所得の6000万円以下の部分について14.21%(所得税10%、住民税4%、復興税0.21%)が適用される。→ 居住用財産の軽減税率の特例
- 住み替えの際に発生する税金を条件付きで先送りすることができる。→ 特定居住用財産の買い替えの特例
といった感じです。
これだけ書かれても訳が分からないと思いますので、まずは①の特例について例を出して説明します。
例題.
取得費2000万円の土地付き戸建てに30年住んだ後、1億5000万円で売却した。
譲渡費用は300万円だった。
このときの税額は所得税・住民税合わせていくらか?
なお、復興税、減価償却については考慮しないものとする。
なんともうらやましい境遇ですが、まずは特例を無視した譲渡所得金額を求めます。
所得金額 = 収入金額1億5000万円 – 取得費2000万円 – 譲渡費用300万円 = 1億2700万円
この居住用財産の軽減税率の特例は、「居住用財産にかかる3000万円の特例」との併用が可能です。
なので次に特別控除3000万円を差し引きます。
1億2700万円 – 特別控除3000万円 = 9700万円
ここで居住用財産の軽減税率の特例が適用されますので、この9700万円を6000万円と3700万円に分けて考えます。
6000万円以下の部分に関しては特例が適用されますので税率は14%で計算します。
6000万円 × 14% = 840万円
そしてここからはみ出た3700万円については長期譲渡所得の20%が適用されますので
3700万円 × 20% = 740万円
となります。
合計の税額は
840万円 + 740万円 = 1580万円
となります。
次に②についてですが、住み替え(居住用財産の買い替え)を行った場合は最初に売った家に対する税金を次の売却まで繰り延べることができるというものです。
ただしこれには条件があり、
- 居住期間が通算10年以上であること。
- 現在住んでいない場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する12月31日までに売却していること。
- 売った年・その前年・前々年に3,000万円特別控除や他の特例を適用していないこと。
- 旧物件の譲渡対価が1億円以下であること。
- 住み替え先の住居の床面積が50㎡以上であること。
- 住み替え先の物件価格が旧物件の売却価格よりも高いこと。
を満たさなくてはいけません。
条件にある通りこの特例は「3000万円の特別控除」及び「軽減税率の特例」と併用することはできません。
あと、譲渡益がゼロであっても確定申告が必要な点には注意が必要です。
ではどんな感じに先送りされるのかについて説明します。
まず、最初に住む家を2000万円で買い、10年以上住んで6000万円(譲渡費用400万円)で売却したとします。
本来であれば
6000万円 – 2000万円 – 400万円 = 3600万円
となり、特別控除3000万円を差し引いても600万円の譲渡益が発生します。
税額は1月1日時点で10年超であれば14%なので、本来であればこの時点で84万円の税金を支払わなければいけません。
しかし、新たに7000万円で家を買い住み替えた場合、買い替えの特例を利用することでこの時点では税金は支払わなくてよくなります。
ではいつ課税されるのかというと、新しく7000万円で買った家の方を売ったときにまとめて課税されることになるわけですね。
その場合、新しく買った家の価格ではなく最初に買った家の取得費をそのまま適用して譲渡益を算出することになります。
要は旧物件の取得費を引き継ぐ形になるわけですね。
例えば上の状況から新しい家を8000万円で売却し、譲渡費用が500万円だとすると譲渡益は、
売却額8000万円 – 旧物件の取得費2000万円 – 新物件の譲渡費用500万円 – 旧物件の譲渡費用400万円 = 5100万円
となります。
繰り延べる際、つまり旧物件の際には3000万円の特別控除は使えませんでしたが、新物件を新たに売る際には3000万円の特別控除が適用できるので、この場合の譲渡益は2100万円となります。
この特例を使わなかった場合とちょっと比べてみましょう。
条件として両方の家で売却年の1月1日時点で所有期間が10年超であった場合という条件をつけておきます。
買い替えの特例を使わなかった場合、旧物件を売却した際には上で述べた通り84万円の税金がかかります。
そして新物件を売った場合には、
8000万円 – 7000万円 – 譲渡費用500万円 = 500万円
が譲渡益となり、10年以上住んでいる場合であれば特別控除3000万円が再度適用でき新物件の売却時の課税はされないことになります。
察しのいい方はお気づきかと思いますが続けます。
買い替えの特例を適用した場合は上で述べた通り5100万円が譲渡益となり、特別控除3000万円を引いた2100万円に14%をかけて税額は294万円です。
このように、買い替えの特例に関しては使えばとにかくお得というわけではなく、状況によっては普通に税金支払うより損をする場合もあるという点に注意が必要です。
軽減税率と買い替えの特例に関しては以上です。
住宅ローンホルダーの救済措置「特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除の特例」。
居住用財産絡みの特例はまだあります。
ここまでは景気よく住んだ家や土地が買値よりも高く売れるときの話をしてきましたが、このご時世そううまくいくとは限りません。
この項では住んでいた家が住宅ローンの残高よりも安い価格でしか売れず、家がなくなって借金だけが残ってしまった場合についての特例、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」について説明します。
税率とか優遇されてもそもそも損してるから意味ないよな?
この特例は税額などの優遇ではなく、条件を満たした不動産を売却して損失が出た場合に、他の所得と損益通算ができます。
そしてその年に通算してもはみ出て損失が残ってしまった場合は、翌年以降3年間の繰越控除が認められます。
例えば、
- 取得費5000万円の家を3000万円で売却するハメになってしまった。
- 譲渡費用は300万円。
- 住宅ローン残高は4000万円。
- その年の他の合計所得金額が700万円。
こういう場合で考えてみると、譲渡損失は、
譲渡価格3000万円 – 取得費5000万円 – 譲渡費用300万円 = ▲2300万円
となり、2300万円もの譲渡損失が発生します。怖いですね。
こちらの特例で適用できる金額の上限が
住宅ローン残高4000万円 – 譲渡価格3000万円 = 1000万円
となります。
この1000万円については当該年度の他の所得700万円と相殺し課税総所得金額はゼロ円となります。
さらに控除しきれなかった分の300万円については翌年に繰り越して翌年分の所得と相殺することができます。
ただし、3年繰り越してなお損失が残った場合は繰り越すことができませんので、いくら残っていようとはみ出した分は消えてしまいます。
なお、この特例で損益通算が認められる限度額は「売却時の住宅ローン残高 – 譲渡価格」と定められていますので、結果的に家を売った資金でローン完済ができた場合はこの特例を受けることができないということになりますね。
この特例を受けるための条件は下記のとおりです。
- 売却年の1月1日時点での所有期間が5年超(長期譲渡所得の条件と同じ)。
- 当該不動産の売却で譲渡損失が出ていて、売却価格が住宅ローン残高を下回る。
- 特例を適用する年の合計所得金額が3000万円以下。
あとこの特例は10年以上ではないということに注意しよう。
相続時の空き家対策「空き家の譲渡の特例」。
ここまでと少し毛色が変わって次は「親が住んでいたけど亡くなった家を空き家のまま放置しなかった人に優遇措置があるよ」というお話です。
昨今空き家問題がけっこう深刻化していますが、その主な原因は「親が亡くなったけど子どもたちは別のところで既に生活基盤があるので誰も住まないまま放置されている」というものです。
更に悪いことに、住宅が立っていると固定資産税が1/6になるという事情から取り壊して更地にすることもできずに放置されてしまっています。
そこでできた特例がこの「空き家の譲渡の特例」です。
この特例は住んでいた人に適用されるのではなく、住んでいた人の相続人に適用されます。
具体的には、「被相続人のが住んでいた家屋で、相続後一定期間内にその空き家を売却した場合、最高3000万円を譲渡益から控除することができる」というものです。
ただし、相続人が3人以上いる場合は控除額の上限が2000万円になってしまいますのでご注意ください。
なお、この特例にはいくつか条件があります。
- マンションなどの区分所有物件ではない。
以下の条件でも空き家対策なのがそこはかとなく伝わってくるよ。
- 被相続人が亡くなるまでその居住用であった物件。
- 1981年5月31日以前に建てられた家屋であること。
- 相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに売却された物件。
- 売却価格が1億円以下であること。
ちなみにこの空き家の特例ですが、「相続財産にかかる譲渡所得の特例(相続税の所得費の加算)」との選択適用となり併用することはできません。
相続財産にかかる譲渡所得の特例については下の通りですのでなんとなくイメージだけは持っておいてください。
相続財産にかかる譲渡所得の特例(相続税の取得費加算)
被相続人から相続または遺贈によって受け取った相続財産を売却したとき、一定の要件を満たすことで既に支払った相続税の一部を、譲渡所得の計算時に取得費として計上できる特例のことです。
例えば被相続人の家を相続して当該物件該当分の相続税を50万円支払った場合、当該物件を売却するときにその50万円を取得費に組み入れることができ、譲渡所得の金額が実際の所得よりその50万円分安くなることになります。
実際に支払う相続税額全てではなく該当物件の分の相続税しか引けないので、実際にはもう少し複雑な計算になるとは思いますが現時点ではざっくりこんな感じで覚えておけばいいかと思います。
スポンサーリンク
不動産周りの税金の話まとめ。
- 不動産は「取得したとき」「持っている間」「貸して儲かったとき」「売って儲かったとき」の4場面で税金がかかる。
- 取得したときの税は「不動産取得税」「登録免許税」「消費税」「印紙税」がかかる。
- 持っている間の税は「固定資産税」「都市計画税」がかかる。
- 貸して儲かったときには不動産所得として「所得税」がかかる。
- 売って儲かったときには譲渡所得として「所得税」がかかる。
- ほとんどの場合は住宅絡みで税が軽減される特例措置がある。
- 受ける方はいいけど覚える方にとっては厄介。
- しっかり区別して覚えよう。
かなり長くなってしまいましたが不動産周りの税金に関してはこんな感じです。
特に住宅が絡んでくると次々と特例が湧いて出てくるので厄介ではありますが、しっかりと区別して覚えていきましょう。
特例のまとめ
| 税目 | 課税主体 | 対象 | 優遇の内容 | 備考 |
| 不動産取得税 | 都道府県 | 宅地 | 課税標準×1/2 | |
| 住宅 | 課税標準-1200万円 | ※1997年4月以前の住宅は控除額が減る。 | ||
| 登録免許税 (所有権保存登記) |
国 | 住宅 | 税率0.4%→0.15% | |
| 登録免許税 (所有権移転登記) |
国 | 住宅 | 税率2%→0.3% | |
| 住宅の 相続・贈与 |
非課税になる | ※土地は特例なし | ||
| 登録免許税 (抵当権設定登記) |
国 | 住宅 | 税率0.1% | |
| 消費税 | 国・地方 | 個人間同士の住宅売買 | 非課税になる | ※業者から買う場合は課税 ※土地は全て非課税 |
| 固定資産税 | 市区町村 | 宅地 | 200㎡以下の部分→課税標準×1/6 200㎡超の部分→課税標準×1/3 |
|
| 新築住宅 | 120㎡以下の部分→課税標準×1/2 | ※新築から3年または5年間 | ||
| 都市計画税 | 市区町村 | 宅地 | 200㎡以下の部分→課税標準×1/3 200㎡超の部分→課税標準×2/3 |
|
| 所得税・住民税 (譲渡所得) |
国・地方 | 居住用 | 特別控除3000万円 | |
| 居住用 10年超 |
6000万円以下の部分→税率14% | |||
| 居住用 10年超 住み替え |
次に売るときまで 税を繰り延べられる |
※併用不可 ※得するとは限らない |
||
| 居住用 ローン残あり |
住宅ローン残高-譲渡価格の分だけ損益通算できる 控除しきれなかったら3年間まで繰り越して控除できる |
|||
| 空き家 (相続人) |
一定期間内に売却すれば 3000万円の特別控除 |
※相続人が3人以上の場合は2000万円 ※マンションは不可 |
次回は不動産の活用や不動産投資について書く予定です。
不動産分野も終盤ですので頑張っていきましょう。
以上です!