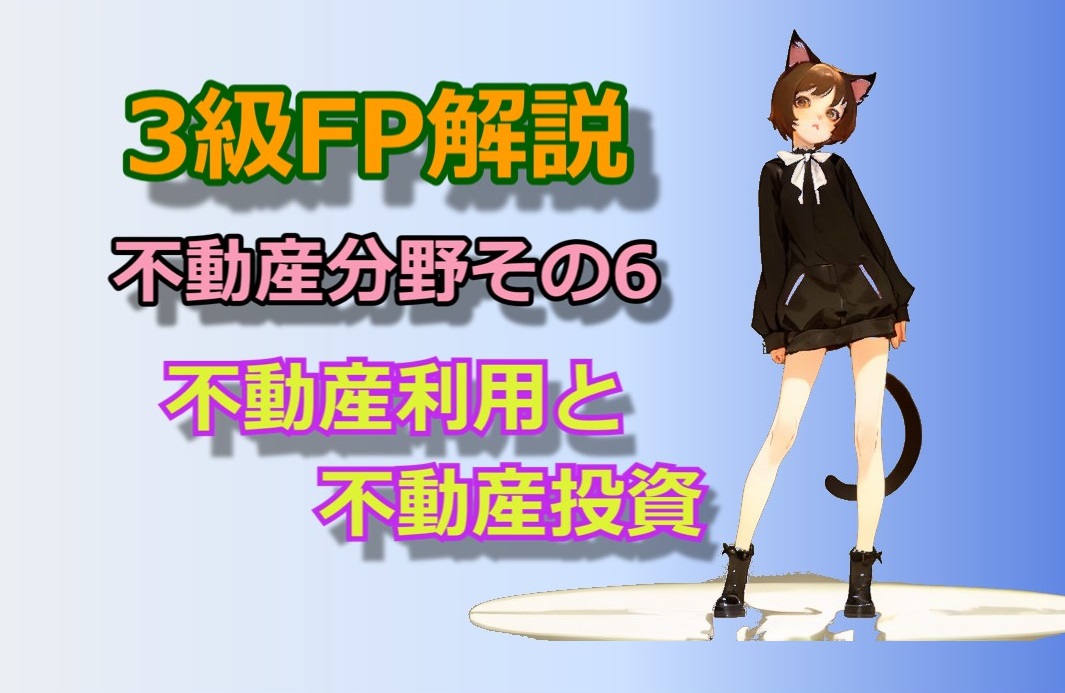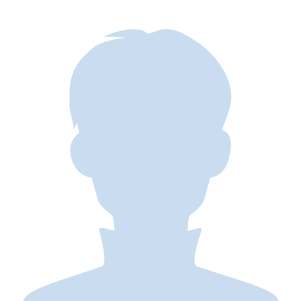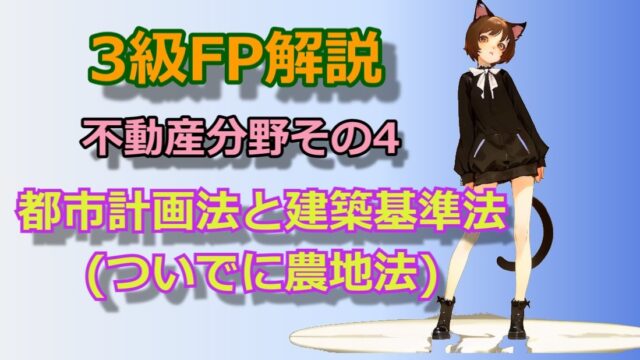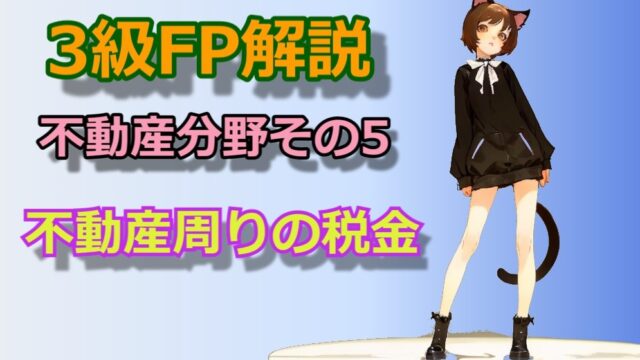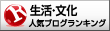今回はFP3級、不動産分野の第6回、この記事で最終回です。
前回は不動産に税金が絡む地獄のパートでしたが、今回の後半部分は若干金融が絡んでくきます。
金融分野にアレルギーのある人は構えてしまいそうですが、3級ではそこまで深堀りする内容ではありませんのであまり身構えずに読み進めていっていただければ幸いでございますよ。
Contents
土地の利用方法とそのメリット・デメリット。
土地はご存知の通り、自分で住んだり売ったりするだけでなくいくつか利用方法があります。
ざっくり言うと、
- 居住用物件を建てて貸し出す。
- オフィスビルなどの事業用物件を建てて貸し出す。
- 駐車場として貸し出す。
などの活用方法があります。
いくつか例を上げてメリット・デメリットを表にまとめました。
どれも感覚的にイメージと一致すると思いますのでざっくり覚えておいてもらえればOKです。
| 活用法 | メリット | デメリット | 備考 |
| 居住用賃貸経営 | 需要が高い。 | 空室リスクがある。 建物老朽化リスクがある。 |
ファミリー向けよりワンルームのほうが収益性が高い。 |
| 駐車場経営 | 借地権・借家権がないためトラブルが少ない。 管理の手間が少なめ。 |
収益性が低い。 競合が増えると特に厳しい。 |
マンションなどの建設業者が隣地買収までのつなぎでやることが多い。 |
| テナントビル経営 | 収益性が高い。 | 景気変動のリスクが大きい。 | |
| ロードサイド店舗 | 場所により高収益。 | 立地、広さを選ぶ。 |
他にも例えば都市部では、コインランドリー、トランクルームなどにする例なんかもありますね。
その土地の特徴に合わせて向き不向きがありますので土地を遊ばせている方はいろいろ検討してみるといいでしょう。
土地活用のための事業手法。
上でいくつか活用方法を紹介しましたが、どれもかなり初期費用がかかりそうです。
もちろん自分で全部やろうとしたらとてつもないお金と労力が必要になるのですが、やはりそこは資本主義社会、お金のにおいがするところにはちゃんと事業者の知恵が働きます。
というわけで、土地活用のための事業手法について解説していきますよ。
実入りが多いが資金と労力が必要な「自己建設方式」。
「自己建設方式」は上で少し述べた「全部自分でやる」方式です。
土地の所有者が自分で企画し、資金も自分で調達、建設も自ら業者を探して発注します。
これは自分に主導権があるので誰かに中抜きされることもなく一番実入りが多くなるやり方です。
しかし資金と労力を自分で捻出するため、手元資金のない人は莫大な借金を背負ってスタートすることになりますし、業者との打ち合わせなどに途方もない労力をかけることになります。
「時間と金を持て余した人がやる事業手法」と覚えておけばいいでしょう。
業者の意向に左右されやすい「事業受託方式」。
「事業受託方式」はデベロッパーに企画と建設を丸投げしてしまう事業方式です。
この方式であれば打ち合わせなどに労力を割く必要はなく、ある程度楽に事業を進めていくことが可能です。
ただし、資金調達は自分で行わなければいけないため、やはり手元のお金がない人は借金スタートになってしまいます。
さらに、企画に自分が関わらずに事業者に丸投げしてしまうことから初期費用が高くなりがちです。
業者が自分でお金を出すわけじゃないですし。
「忙しいけどお金はある人向け」の事業手法と言えるかもしれません。
低利で資金調達ができる「建設協力金方式」。
「建設協力金方式」は、「テナントから建設協力金という名目でお金を借り、テナント料と相殺する形で返済」していく事業方式です。
まず土地の所有者は建設計画を立て、併せて入居するテナントを探します。
テナントと合意したらそのテナントから低利または無利子でお金を借ります。
受け取ったお金を建設資金に宛て建物を建設し、月々のテナント料から決められた返済額を差し引いたお金をテナントから受け取っていくというやり方ですね。
建設協力金方式では、手持ちの資金が不足していても銀行などの金融機関からお金を借りるより利息の負担が抑えられるというメリットがあります。
一方デメリットとしては、建物の仕様にテナントの意向が影響するため、テナント退去後に次の借り主が決まりにくくなるというものがあります。
スポンサーリンク
無理くり投資商品みたいにする「土地信託方式」。
「土地信託方式」は、「土地の所有者が信託銀行に信託してその利益の一部を受け取る」方式です。
つまり信託銀行に丸投げしてしまうわけですね。
この方法のメリットはとにかく労力がかからないこと、そして信託期間が終了したら土地と建物がそのまま所有者の元に戻ってくることです。
デメリットは労力がかからない分実入りもかなり少ない点です。
そして終了時に「正直こんな建物ごと返されても困る」みたいなこともないわけではありません。
というのも土地信託方式では企画から何から全て信託銀行にお任せ状態ですので、企画に所有者の意向は全く反映されないからです。
もちろん信託銀行側も利益を出そうとして運用してくれるのですが、「変換後はアパートとかでも…。」と思っていた所有者の元にやたら尖った商業施設が返ってくる可能性もないわけではありません。
さすがにそうそうあることではないと思いますが、返還時に更地にする義務などはありませんのでその点はご注意ください。
持ち出しなしで物件を一部もらえる「等価交換方式」。
「等価交換方式」は分譲マンションなどでよく見られるやり方ですが、「土地をデベロッパーに差し出す代わりに完成した建物の区分所有権を得る」という方式です。
このやり方のメリットは、何と言っても所有者はお金を出す必要がない点です。
土地はなくなってしまいますが、費用負担ゼロで完成したマンションの土地価格相当分の部屋が割り当てられます。
その部屋は自分で住むこともできますし、人に貸して利益を得ることも可能です。
土地がなくなる代わりにお金も労力も必要としないので「土地に執着のない人向け」の方式と言えるでしょう。
土地を貸すだけ「定期借地権方式」。
「定期借地権方式」はその名の通り「定期で土地を貸す」方式です。
定期借地権を設定するので契約が終了したら土地は返ってきます。
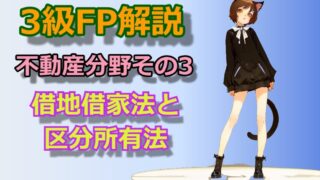
この方式のメリットは手間も労力もお金もかからない点です。
単純に土地を貸すだけですので、建物の用途などに気を遣わなくていいですよね。
デメリットは、建物を利用する分の収益は借り主に行ってしまう分実入りが少なくなる点です。
どういうやり方で収益を得るかについてはこんなところです。
スポンサーリンク
不動産の「投資利回り」。
冒頭でちょっと触れましたが、ここからは不動産賃貸経営(不動産投資)の利回りについて解説していきます。
不動産投資と言っても当然、何でも買って貸せば儲かるというわけではありません。
その不動産を購入する前から「購入金額」と「得られる収入金額」の割合を計算して、その物件が本当に儲かるかどうかの判断基準とするわけですね。
そういった意味ではやることは金融商品への投資と一緒とも言えます。
で、「利回り」については厄介なことに2種類あり、
- 表面利回り
- 実質利回り
が該当します。
この2つの違いをわかっていないと、いざ不動産を買って投資したときに、
何ならマイナスだよチクショー!
みたいな地獄を見ることになるのでしっかり覚えておきましょう。
ではそれぞれ解説していきます。
利益を高く見せるために不動産屋が使う「表面利回り」。
まずは「表面利回り」についてです。
タイトルで結構イヤな書き方をしましたが、個人的には表面利回りを投資勧誘に使う事自体が悪だとまで考えているためこの書き方になりました。
というのも「表面利回り」は、「その不動産にかかるすべての経費を無視した非現実的な利回り」だからです。
表面利回りを求める計算式は、
年間収入の合計 ÷ 投資総額 × 100(%)
となっています。
経費を引かないで利回りを求めるため、必然的に利回りは実際よりもかなり高い数字が出ます。
これは不動産投資の勧誘などで用いられるのですが、表見利回りを鵜呑みにしてしまうと地獄を見ますので投資を考えている方は表面利回りに騙されないよう細心の注意を払ってください。
一応建前上は「確定していない経費を無視するので利回りの計算が楽」という理由で使われるのですが、何も知らない人に向けて経費を無視した利回りをエサにして勧誘することは正直詐欺まがいと言ってもいいと思います。
こっちだけ使えばいいんだよ「実質利回り」。
つぎは幾分かまともに計算される「実質利回り」についてです。
こちらは先程の表面利回りとは違い、経費を計算に含んでいますのである程度精度が上がってきます。
実質利回りの計算式は表面利回りに経費を考慮するだけですので、
(年間収入の合計 – 年間諸経費) ÷ 投資総額 × 100(%)
となります。
経費を引いた分表面利回りより低い数字が出ることは直感でわかりますよね。
もちろん実際に買った後でないと正確な経費がわからないため事前の実質利回りも完璧ではありませんが、少なくとも経費ゼロで算出する表面利回りなんかよりはずっと投資判断には向いています。
ちなみに不動産投資には空室リスクはつきものです。
問題などで空室率や入居率が与えられた場合には、年間収入の合計の方で調整しましょう。
例えば平均入居率80%(0.8)の場合であれば、
(満室時の年間収入の合計 × 0.8 – 年間諸経費) ÷ 投資総額
といった感じになりますし、
平均空室率20%(0.2)という条件が与えられたら、
(満室時の年間収入の合計 × (1-0.2) – 年間諸経費) ÷ 投資総額
といった感じになります。
入居率と空室率がごっちゃにならないようにご注意ください。
不動産の利回り計算については以上です。
「利回り」と聞くとやはり金融分野と絡んでくることもあって嫌な気持ちになってしまう方も多いとは思いますが、債権の利回り計算よりは覚えることも少ないのでだいぶやりやすいと思います。
スポンサーリンク
不動産利用と投資についてのまとめ。
- 不動産の利用方法はいろいろある。
- 規模が大きくなるほど収益性が高くなるが、手間・お金・リスクも同時に増す。
- 土地は持っているが手元資金がない人のための事業方式がいくつかある。
- ただし、手間の少ないものほど収益は少ない。
- 不動産投資の際の利回りには「表面利回り」と「実質利回り」の2種類がある。
- 表面利回りは実態よりも高く出るので不動産屋が勧誘に用いる。
- 表面利回りは架空の最大利回りなので絶対信じるな!
- 実質利回りは経費を引くので多少精度が上がる。
- 不動産の勧誘が来てもどうせぼったくりなので相手にしない。
こんな感じでしょうか。
今回でとりあえず不動産分野の解説は終わりです。
次回以降は「リスク管理」分野について解説していく予定です。
なんとかかんとか3分野終了して半分終わりましたが、残り半分も頑張って書いていきますのでお付き合いいただければ幸いでございますよ。
以上です!