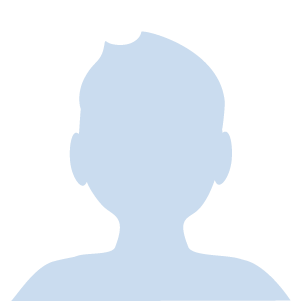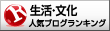私が子供の頃には全く無かったんですが、最近の小学生は1人1台のタブレットもしくはミニノートPCが貸与されています。
これは「GIGAスクール構想」とかいう政策によって強いられた地獄と言っていいと私は思っています。
今回はそのGIGAスクール構想について、我が子の実例を元に個人的な思い(罵詈雑言)を吐き出していこうと思っていますのでお付き合いいただければ幸いでございますよ。
Contents
そもそも「GIGAスクール構想」とは?
まずは諸悪の根源「GIGAスクール構想」について軽く説明しておきますね。
文部科学省のHPからの引用です。
GIGAスクール構想は、1人1台端末や高速大容量の通信ネットワーク等の学校ICT環境を整備・活用することによって、教育の質を向上させ、全ての子供たちの可能性を引き出す「個別最適な学び」と「協働的な学び」を実現することを目的としております。
「子供全員に各々の端末と高速通信の環境を整えて教育の質を向上させよう」というずいぶんふわっとした目的ですが、この曖昧さが噴出する数々の問題点の大元となっていることについては後述します。
要は「子供1人1人に端末を与えてPCに慣れさせておけば、IT絡みですごい子が出てくるのを取りこぼさずに済むんじゃない?」みたいな思惑なんだろうと推察します。
で、これを遂行するためにはもちろん生徒全員の端末代に加え、全学校のWi-FiもしくはSIMでの高速通信環境構築費用が発生します。
第1期にはなんと4800億円もの莫大な予算が計上されており、もちろんこれ1回で終わるわけもなく、端末が古くなれば更新費用もあったり毎月の通信費もあったりでランニングコストも莫大になります。
こんな感じで莫大な予算をかけて肝いりでスタートしたGIGAスクール構想ですが、小学生の我が子やその通っている学校の運用を見る限りでは
完全な金ドブ
と言わざるを得ません。
しかも腹が立つことにChatGPT曰く、我が子が通っている小学校の自治体が成功例として挙げていたんですよ。
正直親の身からすれば「うちの区が成功例に数えられちゃうなら本当の成功なんて皆無じゃん!もう完全に失敗政策!」と思っています。
というわけでここから先の大部分はそのへんの悪口ばっかりとなりますのでご了承くださいね。
GIGAスクール構想を一刻も早くやめるべき理由。
GIGAスクール構想には既に何千億もの税金が注ぎ込まれています。
GIGAスクール構想を取りやめれば既に使ってしまった何千億は返ってこず、なんの成果も得られないまま浪費して終了ということになってしまいます。
それでも私はGIGAスクール構想は一刻も早く取りやめるべきと考えていますので、その理由について小学生の子を持つ親としての実体験から述べていきますよ。
端末の持ち運びがとにかく負担。
我が子が小学校に入学して渡されたSurfaceも現行機もそうなんですが、はっきり言って(物理的に)重いです。
細かく量ったわけではありませんが、タブレットPCにおまけのようなキーボードが付いているだけの端末にも関わらず、我が家で普段遣いしている15.6インチノートと同じくらいの重さです。
今は高学年になって体格も多少は良くなったのでさほど影響はありませんが、入学当初は早生まれでおチビの我が子にはかなりの負担だったと思います。
なぜか我が子の通う小学校では毎日端末を持ち帰ることが義務化されており、その割に週に数回しか使わないため、ただただ重い荷物を持って学校と家の往復を強いられる地獄の日々です。
で、つい最近なんですが我が子の通う小学校でこんなお触れが出されました。
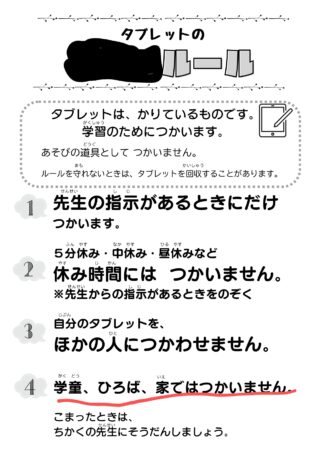
ちなみにここには書かれていませんが、これが添付されていたお知らせには
「家で充電して持ってくるのは従来通りです」
としっかり書かれていました。
頭おかしいと思いましたよ。
「タブレットは学習のために使うものです」っていうのはまあ学校である以上しょうがないんですが、これはそもそもGIGAスクール構想の
「個別最適な学び」と「協働的な学び」を実現する目的
から逸脱しているのではないですかね?
ちなみに画像の一部を消しているのは学校を特定されることを防ぐためなんですが、同じお知らせをもらった親御さんなら一発でわかると思います。
「コイツうちの子の学校の保護者か!」という地味な身バレを覚悟の上で書いていますよ!
スポンサーリンク
現時点での運用が「重いだけの知育玩具」。
上で書いたこととちょっと被るのですが、結局授業中でしか使わせないという点や、それ以前でもそもそも機能の制限が多すぎてまともな用途に使えない端末を生徒に与えたところでなんの役に立つのか、という疑問が出てきます。
そりゃ子供が使うんですから安全を担保するためにフィルタをかけたりある程度の機能制限は必要なのはわかります。
でもこの端末、システムや設定までアクセスが拒否されています。
基本的な操作であるモードや配置の変更もできませんし、スペックの確認すらもできないというクソ仕様になっています。
てかまだ疑ってます。
それで授業中以外では使えない、ネット接続も制限されている、もちろん外部ソフトのインストールも不可、使えるソフトは漢字ドリルと計算ドリルくらいのものです。
こんなものただ重いだけの「知育玩具」に過ぎません。
用途としてはおはじきとか棒とかが入っている低学年用の算数セットよりも狭いわけですから、どう考えても予算の無駄、労力の無駄、電気の無駄です。なんの意味もない。
こんな重量ゴミを毎日持って通学させられている小学校の児童たちが不憫でなりません。
これからも発生する莫大なランニングコスト。
今すぐやめちまえとかこんな話をすると、
とお怒りの方も出てくると思います。
確かにこのGIGAスクール構想にはイニシャルコストとして4800億円(第1期予算、ChatGPT調べ)がかかっています。
今やめてしまうとこの4800億円の大部分が無駄になってしまうという気持ちはわからなくはありません。
しかし、この4800億円をサンクコストとして切り捨ててでもGIGAスクール構想からは撤退すべきと私は考えます。
もちろん上で述べたように実際に子を持つ身として役立っていると全く感じられないからというのも理由なんですが、それ以上に「お金の問題」がついて回るためです。
というのも、莫大な費用はなにも最初期だけというわけではないんですね。
この政策を続けるだけでこの先も莫大なランニングコストがかかり続けることは確定しているんです。
ChatGPTに聞いたところ、端末の更新費用として5年がかりの予算が組まれ、その額は2600億円にも上っているそうです。
つまり、ろくに使いもしない重たいだけの知育玩具未満のゴミを新しいゴミに置き換えるだけのために年あたり500億円の税金が浪費されている状態が今後永続するということになります。
何なら物価はこの先さらに上がっていくでしょうから予算は更に膨らんでいくでしょう。
さらに学校内でのインターネット接続のためにも継続的にお金が飛んでいきます。
年額だと最低240億円ってところですね。は?
もう使ってしまった数千億円はどちらにせよ戻っては来ませんが、少なくとも今撤退すれば端末の更新費用5年2600億円と年間200億円以上の継続的な浪費だけはせずに済みます。
なのでこの無駄な知育玩具浪費祭りはできるだけ早い段階で終了させるべきと私は考えています。
ただの見切り発車なので主導できる人材がいない。
このGIGAスクール構想ですが、ハードありきで既存の学校教育システムの枠組みの中に無理やりハードをネジ込んだだけなのが親の立場から見てもよくわかります。
要は実績作りのための見切り発車でおもちゃを配っただけの政策ですから、従前の教育システムをこなすだけでアップアップだった現場に単に新しい雑務を押し付けただけとも言えます。
そんな状況で上手に端末を活用なんてできるわけがありません。
下地を作らずに上モノだけ放り投げて「自主性を~多様性を~」とか言ってるだけなんです。馬鹿ですよ。
本来のGIGAスクール構想の趣旨に照らして考えるならば、まずはどういうふうに活用していくか、そのために児童生徒に対してどういうふうにネットリテラシーなどの基礎知識を教えていくかなどをある程度策定してから行うべきなのではないでしょうか?
それをせずにさもすごいことやってますみたいな雰囲気だけ出してもなんの意味もないどころか害悪といっても過言ではありません。
しかもタチの悪いことに、親の立場くらい近くにいなければこの害悪が見えてこないこともこの地獄に拍車をかけている一因です。
「タブレット持ち歩いて子供も頑張ってんなあ」
くらいにしか見えないからな。
ただでさえクソ忙しい教員に活用方法から丸投げした状態で上手く事が運ぶと思っているのであれば導入を決定した人間はどこからどう見ても無能と言わざるを得ません。
そもそもただでさえ民間に比べてデジタル化が遅れている学校関係にいきなりデジタルを押し付けたところで、対応できる教員なんてもともとガジェオタだったとかネット民だったなど、趣味の範疇でカバーしている人くらいしか存在しません。
多少は妙なアプリに置き換わっているものもありますが。
つまり運用する現場の教員たちのほとんどが、子供に教えるべきことすら知らない状態で「これ使ってうまいこと教えたれよ」と無茶振りをされている状態なわけです。
さらにそんな中でネット絡みのトラブルを発生させないことは至上命題みたいな空気もあります。
こんな状態でPCやタブレットを子供に与えたところで知育玩具以上の使い方なんかできるわけがないのは明白ですよね。
スポンサーリンク
どうしても続けたいならここからやり直せ!
個人的には今すぐにでも撤退すべきとは思っていますが、既に数千億円のお金を使ってしまった以上あとには引けないという気持ちもわからんではありません。
撤退したら失敗で無駄金だったのが確定して表に出てしまいますし、表にさえ出なければ損失が確定せず(含み損状態で)先送りにできますからね。
なのでどうしてもGIGAスクール構想を引っ込めるのは嫌ということであれば最低限これだけはやらないといけないであろうという提案も気持ちだけしてみようかと思います。
あくまでも撤退が最善策というスタンスは変わりませんが暇な方はお付き合い下さい。
1.学習指導要綱に最低限の目的を明文化する。
GIGAスクール構想が形骸化している諸悪の根源は、現在のGIGAスクール構想の目的が「個別最適な学びと協働的な学びの実現」というあからさまにふわっとしたものになっているという点です。
実際の教育現場からしてみたらこんなふわっとした目的なんて何も無いのと一緒です。
現場の教員にとっては明文化された学習指導要綱こそが最優先にこなすべき義務教育であり、新たな目的が加わってそれを完遂したとしても学習指導要綱の内容が欠けてしまえば怒られることになります。
そんな中で曖昧な教育理念が加わったところでそれをきちんとこなすインセンティブなど皆無です。ただでさえ忙しいのに。
なので学校に端末を配って「頑張れよ!」なんてものは仕事の邪魔にしかなりません。
ならばこのGIGAスクール構想の具体的な目的を、教員がこなすべき学習指導要綱の中に組み入れて、現場で最低限何をするのかを明示する必要があるのではないでしょうか?
で、この政策を作った人間がIT関係の目的が何なのかさえわからずに見切り発車でガワだけ買い与えて中身を現場に丸投げしたからこの惨状になっているわけです。
じゃあ目的は何なのかというと、私が思うに、
- ネット上のコミュニケーションを正しく行うこと。
- 必要な情報や学びたいことを調べられるようになること。
だいたいこの辺に集約されるんじゃないかと思います。
上の2つができるようになれば自ずと「個別最適な学び」や「協働的な学び」なんかは勝手についてきますよね。
結局必要なのはいわゆる「ネットリテラシー」と「ITリテラシー」の基本であって、決して「タブレットは先生の指示があるときだけ使いましょう」という薄気味悪い利用制限ではないはずです。
何なら小学校6年間あるならば低学年のうちは端末無しでリテラシーの座学に徹し、高学年になってから端末を貸与するくらいでいいんじゃないかとも思っていますよ。
かな打ちなんか教えた使う機会ないですし。
2.人材確保と人員の拡充。
学習指導要綱にリテラシー周りを明文化して教員の必須業務にするとなると、現場の教員の人たちは仕事が増えます。
教員全員に新たな項目が加わるとなればそれ相応の研修なども必要になってくるでしょう。
もちろん余裕があれば研修に参加して、具体的に何をどう教えるかを全教員が習得するのが望ましいのですが、何度も言うように教員はそこまで暇じゃない(というよりクソ忙しい)のであまりにも非現実的です。
となると教員のうち何割かが研修に参加してPC周りの指導要綱を現場に持ち帰るという話になると思いますが、そうなると得てして校内で発言力が強くてPCに疎いベテラン教員が若い教員に雑用として押し付けてしまう事になりがちです。
なので結局はITリテラシーの教育を重視しない空気のまま若手教員の負担だけが爆増する(その後若手から辞めていく)という最悪な結果をもたらしかねません。
なので、一番無難なやり方としては副教科の専門教員と似たような感じでリテラシー専用教員を新たに配置するということになると思います。
多分世の中にはパソコン周りについて教えたいという人はいくらでもいると思いますので、あとはその人員に予算をつける覚悟があるかどうかだけですよね。
こう考えるとぶっちゃけ1人1台とか要らなくて、1クラス分くらいのパソコン室を用意しておけば済むんじゃないかとも思いますね。
専門教員もいない状態で開放してたら不良のたまり場になってぶっ壊されるだろうし。
ちょっと話が逸れましたが、結局重量級知育玩具に成り下がらないようにするには、端末の貸与というハード面の整備の前に人員や利用方針などのソフト面を整備しなければいけないという話ですね。
まあ今から国や自治体が新たに予算をつけて方針転換なんてできるわけもないでしょうから、現時点での最善策は完全撤退という考えに変わりはありません。
ほっといたら更に垂れ流すんだよ?
3.大成功の自治体があるなら全国で丸パクリ。
私の住む自治体がAIの判断では成功事例とされていましたが実際は全く成功していないという話は上で少し触れました。
しかしAIが他に成功事例として挙げていた自治体は他にもあります。
現段階でそれらの自治体の運用事例が成功かどうかを判断する術は私にはありませんが、もしちゃんとした成功事例があるとしたらそれを全国全自治体に共有し、何なら丸パクリさせるくらいの荒療治が必要だと思います。
多様化を謳っているGIGAスクール構想の趣旨とはずれてしまうかも知れませんが、支払ってしまった予算を最速で有益なものにするにはおそらくこれしか方法はないと思います。
現場に成功体験を覚えさせ、新しいことをしたければそのうえで発案するという形にしなければいつまで経っても貸与端末は知育玩具の域を脱することはできません。
要は「現時点での成功自治体を真似できて初めてGIGAスクール構想のスタート地点」であり、それすらできないのであればPCで教育の多様化などただのファンタジーです。
なので現状を鑑みれば本来ならば切り捨てて撤退すべきなのですが、どうしても割り切れないという場合には丸パクリ戦法が最も早く結果を出せる方法なので一応提案してみた次第です。無理でしょうけど。
スポンサーリンク
令和の大愚策GIGAスクール構想のまとめ。
- 端末貸与しかしないGIGAスクール構想は、成功例として挙げられることもあるような自治体でもこの有り様。
- 現状では貸与端末はただの重量級知育玩具かそれ以下のゴミ。
- これに何千億とか狂気の沙汰。
- 失敗の理由はソフト面を無視してハードだけを突貫で整えたこと。
- 世間で反対の声が大きくならないのは保護者くらいしかこの歪みに気づかないから。
- でも何千億ドブに捨ててるよ!
- もし成功させたいのなら「学習指導要綱への組入れ」と「専門人員の拡充」が最低条件。
- もし成功した自治体があるなら全国のモデルにするくらいやらないとだめ。
- でもどうせできないんだから今すぐ撤退したほうがマシ。
こんな感じでしょうか。
教育にもパソコンにも興味がない人はたとえ保護者であってのこの歪みに気づかないかも知れません。
また、何千億もの税金が投入されていることを知らない保護者も多いでしょう。
なのでこの世紀の大愚策に対して世間はあまり大きな声を挙げている様子は見られません。
これは先ほども書きましたが、教育現場とつながりのない人にはその無駄さ加減が全く見えないからだと思います。
私は保護者の立場から、子供がどんな端末を持たされどんな使い方をしているかを(我が子の学校についてだけは)知ることができます。
もちろん私は他の学校の運用はわからないのでChatGPTに成功例として出されなければ学校側の運用の問題と捉えていたかも知れません。
となると小学生の親以外の国民(有権者)にはこの無駄遣いを知る機会はほとんど与えられないわけですよね。
「教育」という分野においては予算が潤沢にないイメージがあり、しかも教育分野からの予算を削るというのは「やってはいけない悪」という風潮もあります。
有効に使えてこその聖域なはずなのに。
本来であれば「聖域の予算を削ること」よりも「聖域に無駄金を垂れ流すこと」のほうが悪として叩かれまくられるべきなんですけどね。
というわけで感情的な罵詈雑言が多くはなりましたが、個人的な意見として「GIGAスクール構想なんてできないんだしさっさと撤退せよ!」という中年の主張をお送りいたしましたが皆様どうお考えでしょうか?
反論異論がおありの方はTwitterにでもご意見をいただけたらと思います。
また、「うちの自治体ではこんなふうに有効活用できてるよ!」という実例がございましたらぜひご教示下さい。
以上です!