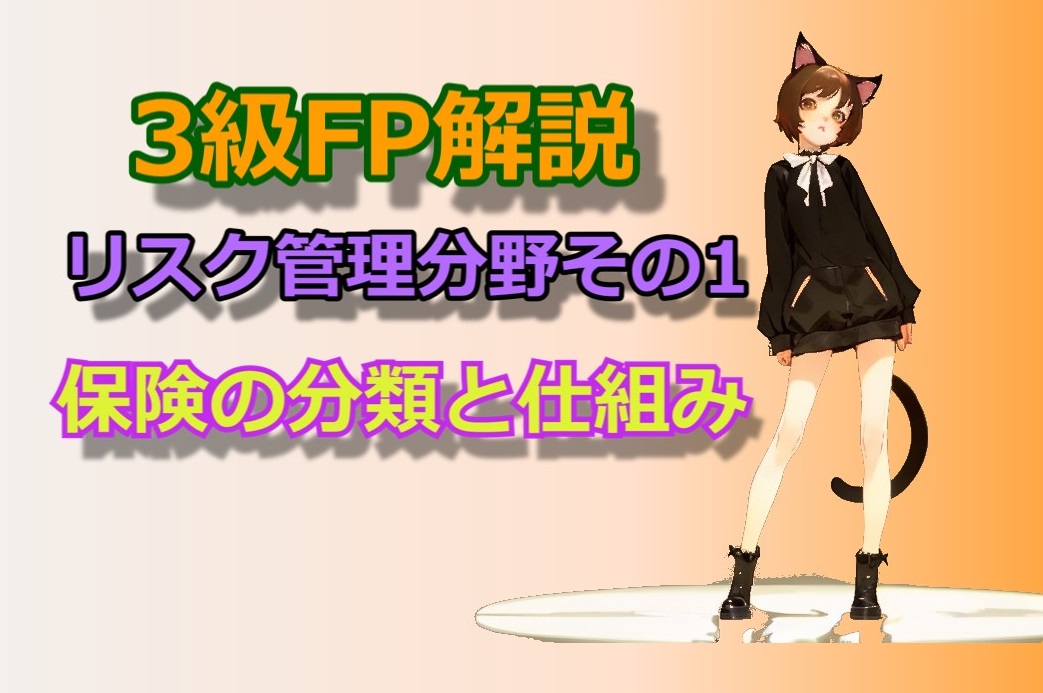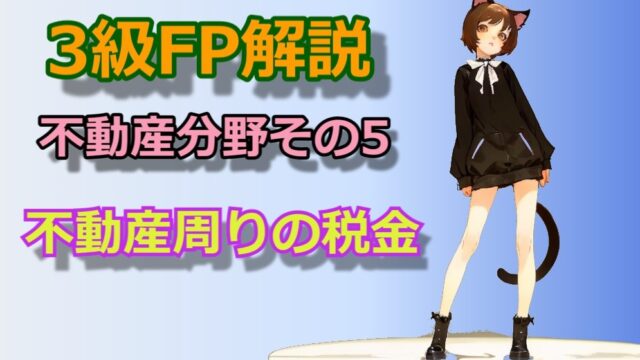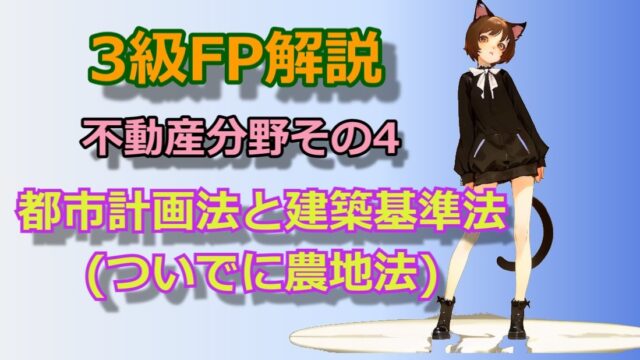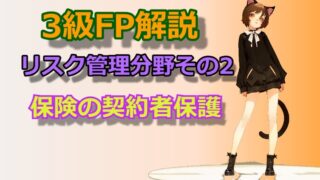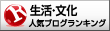FP3級の解説記事もなんとかかんとか3分野まで終えることができました。
前回までは不動産分野をやってきましたが今回からは「リスク管理」分野について解説していきますよ。
ややこしいのには変わりありませんが、金融や税金と比べたら幾分かマシだとは思いますので頑張っていきましょう。
そもそも「リスク」とは?
「リスク」と聞くと通常は「危険」みたいなイメージがありますが、お金に絡む話では「先々の不透明性」という意味で使われることが多いです。
要は「未来のことなんかわからんよ!」というイメージ全体を「リスク」と呼ぶわけですね。
そして特に保険の話になると「この先起こるかもしれない悪いこと」という意味を主に帯びてきます。
そしてその「様々なリスクに対して備えをしておこう」というのが保険の役割というわけです。
主に保険で備えるべきリスクというのは下記のようなものがあります。
まずは「人」に関わるリスクだと、
- 近めの将来に死んでしまうかもしれないリスク
- 逆に予想以上に長生きしてしまうかもしれないリスク
- 病気や怪我で働けなくなってしまうかもしれないリスク
などがあります。
そして「モノ」に対するリスクは、
- 家が火事で燃えてしまうかもしれないリスク
- 事故で自家用車が廃車になってしまうかもしれないリスク
- その他の資産が盗まれたり消失するかもしれないリスク
などがあります。
さらに自分のものではなく、「他人の財産を侵害してしまう」リスクなんかもあります。
- 他人に怪我をさせてしまう、死亡させてしまうかもしれないリスク
- 他人の物を壊してしまうかもしれないリスク
なんかがそうですね。要は損害賠償系です。
こういった不測の事態に必要になるのは第一にお金ですので、そのお金をある程度は保険で賄うことができますよ、というお話ですね。
保険の種類。
保険と一口に言ってもその種類は多岐に渡ります。
なので数多ある保険をその性質によって分類していますのでこの項ではそれについて触れていきますよ。
「公的保険」と「私的保険」。
まずは保険の主体による分類です。
「公的保険」は読んで字のごとく、国や自治体など「公的な機関が運営している保険」のことです。
- 国民保険や健康保険などの社会保険
- 国民年金や厚生年金などの公的年金保険
- 公的介護保険
- 雇用保険
- 自賠責保険
などが該当します。
日本では「国民皆保険制度」が採用されており、特に社会保険と年金保険は原則として全国民が強制的に加入させられることになっています。
まあ税金みたいなもんですね。
ちなみに介護保険は40歳以上の国民、雇用保険は一定の要件を満たしたサラリーマンが強制加入となっています。
一方の「私的保険」は公的機関以外、つまり「民間会社が運営主体となっている保険」のことです。
こちらは
- 生命保険
- 個人年金保険
- 医療保険
- 民間介護保険
- 損害保険
- がん保険
- 火災保険
- 自動車保険
などなど需要に応じて数多くの種類があります。
これらは基本的には自分のために任意で加入する保険です。
なぜこういった分け方をするのかぶっちゃけてしまうと、「公的保険はリスク管理分野とは別に『ライフプランニング分野』でのメイン要素になっている」ためです。
なので今やっている「リスク管理」分野では主に「私的保険」の内容を解説していくことになります。
私的保険における「分野」の区別。
そして主に種類の多い私的保険については、第一~第三分野というように数字で分類されています。
「いきなり数字で分類されても…。」と思うのは当然かと思いますがこればっかりはどうしようもありません。
覚え方としては、
- 人の生死に対して保障する保険が第一分野
- 事故等で発生した物的損害に対して保証する保険が第二分野
- その他が第三分野
という感じで覚えてください。
別にわかり易くないから言わんでいいぞ?
基本的に第一分野は生命保険会社、第二分野は損害保険会社で取り扱います。
第三分野はそれぞれの保険によって生命保険会社が扱うか損害保険会社が扱うかが異なり、両方で取り扱いがある保険も存在します。
それぞれの扱いはこんな感じです。
| 分野 | 保険の種類 | 取扱会社 |
| 第一分野 | 終身保険 | 生命保険会社 |
| 定期保険 | ||
| 個人年金保険 | ||
| 養老保険 | ||
| 第二分野 | 火災保険 | 損害保険会社 |
| 自動車保険 | ||
| 自賠責保険 | ||
| 第三分野 | 医療保険 | 両方 |
| 介護保険 | 主に生命保険会社 損害保険会社は主に特約として提供 |
|
| がん保険 | 主に生命保険会社 損害保険会社はは主に特約もしくは短期商品として提供 |
|
| 傷害保険 | 主に損害保険会社 生命保険会社もたまに特約で扱う |
|
| 所得補償保険 | 主に損害保険会社 生命保険会社は「就業不能保険」などの類似品を提供 |
一応書いておきましたが、第三分野の保険商品に関しては取扱会社を覚える必要はありません。
「第一分野は生命保険会社」「第二分野は損害保険会社」という感じで覚えておけば充分だと思います。
スポンサーリンク
保険を成り立たせる仕組み。
保険会社は、契約者に何らかの不幸があったときにそれなりに大きい金額を支払います。
それは不幸に遭っていない人も含めた契約者から支払われた保険料から賄っているわけですが、これを成り立たせるためのルールが2種類ありますのでそれについて解説します。
大数の法則。
「大数の法則」自体の意味は、「サンプルが少ないとみつけられないような法則でも、サンプルが多くなることで一定の法則が見いだせる」ということなんですが、保険はこの法則にのっとって事業を成り立たせているわけですね。
「30代男性の死亡率は総じて◯%くらいだから1000万円の保険なら保険料は〇〇円だな」
といったように事例から法則を見出して保険料などを設定していきます。
現段階では「保険の内容は大数の法則に則って条件が設定されている」といったイメージを持っておけば大丈夫かと思います。
収支相等の原則。
次に「収支相等の原則」ですが、こちらも保険の条件等を設定するためのルールです。
内容としては、
「契約者全体で見ると、払込保険料は支払保険金及び運営経費と等しくなる」
というものです。
つまり、
払込保険料(収入) = 支払保険金(支出) + 運営経費(支出)
で収支が釣り合うということですね。
まあ運営経費に何を含むかというのは保険会社のさじ加減ですからぶっちゃけ厳格に運用されているとは言い難い部分はあります。
外貨建ての貯蓄型保険とか最悪です。

話が逸れましたが、保険の仕組みとしては(建前上は)保険会社の収入と支払が釣り合うように設計されているものだということは覚えておいてください。
スポンサーリンク
保険の基礎知識と仕組みのまとめ。
- 保険は不幸に遭った人の損失を契約者全体で賄う仕組み。
- 保険は人や物、損害賠償など様々なリスクに対して保障する。
- 保険は「公的保険」と「私的保険」に分かれ、私的保険は更に「第一~第三分野」に分類される。
- 保険は「大数の法則」と「収支相等の原則」の2つによって設定される。
こんな感じでしょうか。
本当は今回の記事に「契約者保護の仕組み」の項目も入れたかったんですが、一緒にしてしまうとバカ長くなりそうだったので分けることにしました。
というわけで次回は「保険契約者保護」に関しての内容をメインにして書いていく予定です。
こちらは聞き慣れない単語とかも出てきたりしてちょっと面倒ではありますが、タックスや金融よりはマシだと思います(2回目)なので頑張っていきましょう。
以上です!