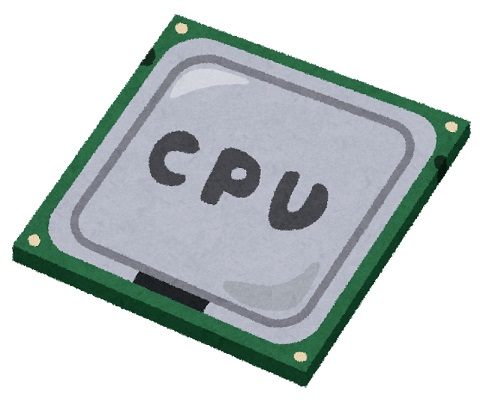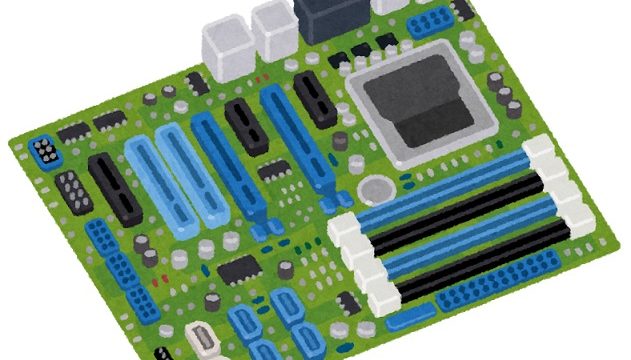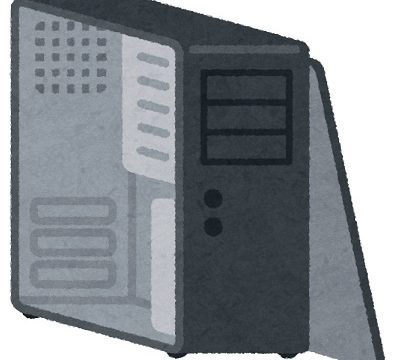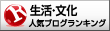自作PCを組むときに多くの人が一番初めに決める主要パーツであるCPUですが、自作初心者の人が初めて組む際には何を選べばいいのか迷うと思います。
今回はCPUの選び方を初心者向けになるべく簡単に説明していきますよ。
結論から言うと、
ざっくりの予算とざっくりの求める性能でざっくり決める
ということなのですが、それで終わらせるにはあんまりなのでいくつか具体的にポイントをまとめていきますのでお付き合いください。
あと、この記事の内容は私個人の偏見が多分に含まれています。
そういった前提の元お楽しみください。
Contents
CPUのメーカーは2社。今はどっちでもいいよ!
現在CPUを製造しているメーカーは
- Intel
- AMD
の2社で、自作PCのCPUもこの2社から選ぶことになります。
長らくCPU業界の覇権を握っていたのは「Intel Coreシリーズ」で、ちょっと前まではIntel一強と言われていました。

しかし、2017年にAMDが「Ryzenシリーズ」をリリースしてから2社のメーカーには性能の差はほとんどなくなります。
何ならRyzenのほうが同性能帯では価格が少し安くなっているため、自作PC市場でのCPUシェアでAMDが逆転しているんだそうです。
一方IntelのCoreシリーズは長らく覇権を取っていたので、Intel製CPUで自作している人が多く存在します。
ネット上に転がっている情報量もまだIntelが多く、初めて組む人には安心材料と言えるでしょう。
Intel(Coreシリーズ)とAMD(Ryzenシリーズ)のどちらがいいかという話では、2020年2月現在でいうとどちらを選んでもOKです。
ざっくりポイントを挙げるとすれば、「コストパフォーマンスのAMDか安心感のIntelか」というところでしょうか。
追記:2023年4月現在ではAMD製CPUの情報も出揃っており、価格差もメーカーによるくくりではなくなってきています。
メーカーごとではなく商品ごとのコストパフォーマンスを考えてCPUを選ぶのがいいでしょう。
メーカーが決まったらCPUのランクを決めよう。ここは財布と相談!
CPUランクの種類。数字が大きいほど高性能高価格。
メーカーを決めたら次はどのCPUにするかを具体的に選定していきます。
CPUが決まると完成品のスペックがぼんやりと固まってきますので、まず完成品で何をするのかということがCPU選びに置いて肝になってきます。
IntelとAMDそれぞれのCPUにはランクが存在し、各ランクにはそれぞれ異なった名前がつけられています。
| Intel | AMD | |
| ローエンド (価格重視) |
||
| ミドルレンジ (バランス型) |
Core i3、Core i5 | Ryzen3、Ryzen5 |
| 15,000円~26,000円程度 | 9,000円~3万円程度 | |
| ハイエンド (性能重視) |
Core i7、Core i9 | Ryzen7、Ryzen9 |
| 45,000円~9万円程度 | 28,000円~5万円程度 |
こちらを見るとおわかりかと思いますが、ミドルレンジ以上のCPUにはCore i シリーズ、Ryzenともに3・5・7・9と数字が振ってあります。
それぞれ数字が大きいほど高性能高価格、各数字に対応したライバル商品という構成になっています。
それほどヘビーな用途でないのであれば数字の小さなモデルを選んでコストを抑えることが肝になりますし、高画質のゲームをしたり動画編集をしたりするのであればコストを受け入れて大きな数字のモデルから選ぶことになります。
尚、サーバーとかデータセンターとかに用いられる別シリーズのCPU(Xeon、Threadripper)もありますが、個人用途であまり用いられないのと訳がわからなくなるのでここではすべて無視します。
CPUを買う際に比べる点は、
- グラフィック機能(GPU)の有無
- コア数・スレッド数
- クロック周波数
- クーラー付属の有無
- 価格
あたりでしょうか。
まずGPUの有無ですが、CPUにはグラフィック機能が搭載されているものといないものがあります。
GPUが搭載されていて、グラフィック性能を重視しなければ別途グラフィックボードを購入する必要はありません。
逆にGPU非搭載であれば何かしらのグラフィックボードを別途購入しなければ画面出力ができません。
- Coreシリーズは基本的にGPU搭載、ただし型番に「F」がついているものは非搭載
- Ryzenシリーズは基本的にGPU非搭載、ただし型番に「G」がついているものは搭載
と覚えておけば無駄なコストを抑えられるでしょう。
CPUに内蔵されているグラフィックは基本的に性能は低いですが、IntelとAMDを比較するとAMDのほうが優れていますので、内蔵でいいからなるべく高性能がいいという方はRyzenシリーズが有力な選択肢になってきます。
コア・スレッド・クロック周波数に関しては、現時点ではざっくり数字の大きいほうが高性能という認識で構わないと思います。
優先順位としては「コア>スレッド>クロック周波数」ですが、ゲームなどは単一コアあたりのクロック周波数が求められたりするので、一概には言えないところがややこしいです。
CPUクーラーについては、ミドルレンジのCPUはクーラーは付属していますが、Coreシリーズ一部モデル(「K」と記載のあるもの)とRyzenの一部上位モデルには付属クーラーはありません。
上位モデルを買うときはCPUクーラーを別途買わなければいけませんのでご注意ください。
ちなみにクーラーの性能もAMDのRyzenシリーズのほうが優秀なんだそうですが、高負荷の作業をしないのであればここもあまり気にしなくていいと思います。
そして自作パソコンで一番気にしなければいけないのが価格です。
自作PCは自由度が高い分、あれもこれもと欲張るとコストが青天井で上がっていきますので、必要な性能と懐具合を吟味しながらパーツを選ぶことが一番大事で一番難しいところです。
というわけでこれらの点をを気にしつつ各レンジのCPUについて見ていきますよ。
格安でパソコンを組むなら廉価モデルだが性能は推して知るべし。
追記:2023年4月に調べたところ、新世代CPUでは廉価モデルはほとんど流通していないようでした。
一応Celeron、pentiumともに現行のソケットに合う商品もあるにはありましたが、4コア以上が主流の現在においてCeleronが2コア2スレッド、pentiumが2コア4スレッドとなっています。
価格はCeleronで1万円、pentiumで13,000円程度となっており、4コア8スレッドのCore i3が15,000円程度と考えるとわざわざ自作でこちらを組む意義は薄いのかなと思います。
以下の記事は取り消し線を入れておきますが、内容については当時の雰囲気をお楽しみ下さい。
まずはローエンド帯のCPUについて見ていきますが、こちらはとにかく安くあげたい方向けのCPUですので、性能についてはお察しです。
基本的にはパソコンで負荷の多い作業をしない場合に用いられるので、書類作成程度でしかパソコンを使わずコストを下げたい法人用などに使われることが多いです。
個人的にはこのランクでPCを組む意味はあまりなさそうに思いますが需要はあるかもしれないのでサラッと説明します。
CPUは似たよう名前で種類がたくさんありますので主だったものを抜粋しています。
※価格は執筆当初の目安です。実勢価格は短いスパンで目まぐるしく変わりますので参考程度にしてくださいね。
ローエンドの中でもいくつかのランクがあります。
最安はIntelのCeleron G4900ですが、それより少しだけ性能の高いCeleron G4930がほぼ同価格帯で市販されています。
性能を考えずコスト削減だけを求めるならこの2つが有力な選択肢で、どちらかといえばG4930のほうがコストパフォーマンスが良さげです。
G4950なら同じくらいの値段のPentium Gold G5420のほうが高性能なので選択肢から外れるでしょう。
処理性能だけで見るとざっくり「Pentium>Athlon>Celeron」となっており、グラフィック性能ではVega3のほうがUHDよりもだいぶ優れているので、全体で見るとやはり値段なりのパフォーマンスなのかな、という感じがしますね。
一方のAMD製品ですが、今回は1つしか挙げていません。
本来は第2世代のGEシリーズを挙げる予定だったのですが、書いているうちにより高性能な第3世代の方が実勢価格が安くなってしまっていたため外しました。
とりあえずAMD製品のローエンド帯ではAthlon 3000Gだけ選択肢に入れておけばいいと思います。
コスト削減を追い求めるなら「Celeron G4930」、安価でも多少ゲームをするという場合は「Athlon 3000G」に落ち着くのではと思います。
ローエンドの中で処理性能を求めるなら「Pentium Gold G5620」と言いたいところですが、ミドルレンジのCore i3と価格がほぼ変わらないので個人的にはあまりおすすめできません。
処理性能を妥協して「Pentium Gold G5420」にするか、思い切ってミドルレンジCPUにするかの2択になるでしょう。
ローエンドCPUの選び方(2020年2月現在)
とにかく安くあげたいなら「Celeron G4900」か「CeleronG4930」。軽くゲームをやるなら 「Athlon 3000G」。安い中で処理性能を重視するなら「Pentium Gold G5420」。
ミドルレンジは自作PCのボリュームゾーン。選び甲斐もあるよ!
Intelの「Core i3、i5」とAMDの「Ryzen3、5」の4種類は一般的にミドルレンジに分類されます。
コストと性能のバランスがいいためこのカテゴリのCPUで自作する人は多く、初めて組む人もこの辺から選ぼうと考えている人も多いのではないでしょうか。
その分数種類も多く選ぶのも大変ですが、悩んでいる時間も楽しいものなので選び甲斐もあるでしょう(多分)。
というわけでこちらも主だった製品を並べて見ていきますよ。
| コア数 /スレッド数 |
周波数 | GPU | クーラー | 価格帯 | |
| Core i3 12100F |
4/8 | 3.3GHz | なし | あり | 15,000円程度 |
| Core i3 13100F |
4/8 | 3.4GHz | なし | あり | 17,000円程度 |
| Core i3 12100 |
4/8 | 3.3GHz | UHD730 | あり | 2万円程度 |
| Core i3 13100 |
4/8 | 3.4GHz | UHD730 | あり | 21,000円程度 |
| Core i5 12400F |
6/12 | 2.5GHz | なし | あり | 23,000円程度 |
| Core i5 13400F |
10/16 | 2.5GHz | なし | あり | 28,000円程度 |
| Core i5 13400 |
10/16 | 2.5GHz | UHD730 | あり | 33,000円程度 |
| Core i5 13500 |
14/20 | 2.5GHz | UHD770 | あり | 36,000円程度 |
| Core i5 13600KF |
14/20 | 3.5GHz | なし | なし | 42,000円程度 |
| Core i5 13600K |
14/20 | 3.5GHz | UHD770 | なし | 46,000円程度 |
| Ryzen3 4100 |
4/8 | 3.8GHz | なし | あり | 9,000円程度 |
| Ryzen3 4300G |
4/8 | 3.8GHz | Vega8 | あり | 16,000円程度 |
| Ryzen5 5500 |
6/12 | 3.6GHz | なし | あり | 14,000円程度 |
| Ryzen5 5600G |
6/12 | 3.9GHz | Radeon Graphics | あり | 2万円程度 |
| Ryzen5 5600X |
6/12 | 3.7GHz | なし | あり | 23,000円程度 |
やはりボリュームゾーンだけあって結構な数があります。特にIntelが多いですね。
ズラッと並べられてもイマイチわかりにくいので大まかな違いを解説してみます。
まず2社のCPUに共通する法則は、
- 3と5なら5のほうが高性能。
- 4桁(または5桁)の数字の上1桁がそのシリーズの世代を示す。大きいほうが新世代。
- 同じメーカー内でCore i またはRyzenに続く数字が3同士、5同士であれば、さらにあとに続く4桁または5桁の数字のうち下3桁の数字が大きいほうが概ね高性能。
- コア数が多いほうが高性能。
- 同コア数であればスレッド数が多いほうが高性能。
- 同コア数同スレッド数であればクロック周波数が大きいほうが高性能。
といった感じです。
次にIntel Core i シリーズの法則としては、
- 4桁の数字の後に「F」のついているモデルはグラフィック機能がなく、少し安い。
- 「K」のついているものは上位モデルでクーラーがついていない。
- 12000番台が第12世代、13000番台が第13世代。
つまり、特に記載がなければグラフィック機能もクーラーも標準で搭載されているので、アルファベット付きのモデルはオプションを削ったものと考えてください。
一方のAMD Ryzenシリーズはというと、
- 4桁の数字の後に「X」のついているものは上位モデル。
- 「G」のついているものはグラフィック機能搭載。
- 4000番台より5000番台のほうが新しい。
クーラーは搭載していますが、グラフィック機能は基本的に非搭載です。
RyzenシリーズはRyzen3の種類を絞っているため、Intel Core iシリーズに比べてラインナップが少なくなっています。
これはIntelが色んな商品を出して幅広く作っているのに対し、AMDは
「3くらいなら周波数のランクはたくさん必要ないでしょ?」
「上位モデル使う人はグラボも上位のが必要になるでしょ?」
というスタンスで、売れ筋の商品にリソースを割いていることが伺えます。
軽めのゲームなら「3」でOKだが各ゲームの推奨環境は調べておこう。
ちなみに私が前に使っていた家の自作デスクトップの構成は「Core i3 8100」でしたが、動画編集や高画質のゲームはしなかったため特に不便はありませんでした。
ただ、「信長の野望 創造 with パワーアップキット」を始めたときは、内蔵GPUでは画像処理が追いつきませんでした。
そのため別途グラフィックカード「GTX 1050Ti」を増設して使用していました。
ちなみにこのグラフィックカードは当時、全体では中の下くらいの性能で、スリム型のPCに組み込めるタイプ(ロープロファイル対応)の中では上から2番目の性能の商品でした。
わりと現在でもある程度の用途に使えるのでいい商品だったと思っています。
信長の野望くらいの用途であれば、CPU性能は4コア8スレッドのCore i3やRyzen3で間に合いますが、Intelの内蔵GPUでは画像処理に難があるくらいの認識で構わないと思います。
Intelは現在12~13世代が中心なのでグラフィックも当時よりは進歩していると思いますが過信は禁物です。
一方、私が別に所有しているノートパソコンは、
- Ryzen5 3500U(4コア8スレッド、2.1GHz)(※「U」はモバイル用の記号で若干低性能)
- Vega8
の構成ですが、画質設定を標準画質にすれば問題なく動いています。
ですので「信長の野望 創造」をプレイする程度であれば、
- Core i3 12100F(別途安めのグラフィックボードを乗せる。)
- Ryzen3 4300G
あたりが丁度いいスペックではないでしょうか。
ちなみに私は最新作をプレイしていないのでわかりませんが、もしかしたら内臓のVega8ではキツイかもしれません。
その場合はやはりグラフィックボードを別で付けたほうが安心かもしれませんね。
ちなみにドラゴンクエストⅩはVer.3までプレイしていましたが、こちらは数世代前のIntel内蔵GPU HD2500で普通に動いていました。
現在の必要環境はHD4000以上とされていますので、現行世代のUHD730であればとりあえず動くはずです。ただし推奨環境ではIntelの内蔵GPUは含まれません。
もしゲーム目的でパソコンを組むのであれば目的のゲームをWEBで調べて必要環境や推奨環境に合ったCPUを選べばひどい目に遭うことはないでしょう。
信長の野望の話は一体何だったんだよ…。
高画質ゲームはいずれにせよ内蔵GPUでは対応できない。
これを読んでいる方の中にはもっと高画質のゲームを楽しみたいという方もいるかもしれません。
結論から言うと、高画質ゲームをするのであれば内蔵GPUでは太刀打ちできません。
そうなるとある程度の性能があるグラフィックボードを載せることになると思うのですが、ある程度のグラフィックボードの性能はある程度のCPU性能がないと引き出しきれないという悲しい現実があります。
せっかくのグラフィックボードの性能を遊ばせてしまうのはまさにお金をドブに捨てるようなものですので、買いたいグラフィックボードの性能に合ったCPUを選びましょう。
グラフィックボードランクもざっくりとローエンド、ミドルレンジ、ハイエンドに分類されていることが多いので、それに合わせたレンジのCPUを選べば問題ないと思います。
細かいところまで吟味しだしたらきりがないので割とざっくりでいいと思いますよ。
ミドルレンジCPUの選び方(2023年4月現在)
- 軽めのゲームだけならやや安めの「Ryzen3 4300G」あたり。
- グラフィックをもう少し求めるなら「Ryzen3 4100」で別途グラボを挿す。
- 重めのゲームをするなら「Ryzen5 5500」+別途グラボがコスパ良さげ。
- 何だかんだRyzenのほうが安いな…。
- やりたいゲームが決まっているなら推奨環境を調べよう。
ハイエンドはゴリゴリのゲーマーか動画編集者向け。9とか何に使うの?
さていよいよこちらからは夢のハイエンドCPUです。
自作PCを組むのであれば一度は組んでみたい夢のハイスペック機ですが、通常の用途で必要になることはあまりないでしょう。
このクラスのCPUが必要になってくるのは、
- 高画質3DゲームやVRをストレスなく楽しみたい。
- 動画をゴリゴリ編集したい。
などのかなり高負荷な作業を必要とする場合です。
もしこれらの用途に使う予定がないのであればわざわざハイエンドCPUを選ぶ必要はあまりなさそうです。使いこなせなければ高いだけですからね。
では例によってこのクラスの主なラインナップを見ていきますよ。
| コア数 /スレッド数 |
周波数 | GPU | クーラー | 価格帯 | |
| Core i7 13700F |
16/24 | 2.1GHz | なし | あり | 52,000円程度 |
| Core i7 13700KF |
16/24 | 3.4GHz | なし | なし | 55,000円程度 |
| Core i9 13900KF |
24/32 | 3.0GHz | なし | なし | 77,000円程度 |
| Core i9 13900KS |
24/32 | 3.2GHz | UHD770 | なし | 11万円程度 |
| Ryzen7 5700X |
8/16 | 3.4GHz | なし | なし | 26,000円程度 |
| Ryzen7 5700G |
8/16 | 3.8GHz | あり | なし | 27,000円程度 |
| Ryzen7 5800X |
8/16 | 3.8GHz | なし | なし | 32,000円程度 |
| Ryzen7 5900X |
8/16 | 3.7GHz | なし | なし | 41,000円程度 |
| Ryzen9 5950X |
16/32 | 3.4GHz | なし | なし | 72,000円程度 |
| Ryzen7 7700X |
8/16 | 4.5GHz | なし | なし | 44,000円程度 |
| Ryzen7 7900X |
12/24 | 4.7GHz | なし | なし | 61,000円程度 |
| Ryzen9 7950X |
16/32 | 4.5GHz | なし | なし | 83,000円程度 |
まずIntelです。
第13世代のintel CPUは総じてコア数が多く、前世代と比べるとわかりやすくパワーアップしていますね。
i7を選ぶのであれば周波数が5割くらい高くて価格差が3,000円程度しかないので、13700KFの方を選ぶほうがお得な感じがしますね。
CPUクーラーを別途購入する必要がある点にはご注意下さい。
i9の方は価格差が4万円くらいあるのでこ、だわりがなければ13900KFのほうがお得感があります。
AMDについては5000番台(AM4)と7000番台(AM5)でソケット型が異なり、互換性がないのでCPU、マザーボードを選ぶ際には間違えないようにご注意下さい。
私が現在のパソコンを組んだ頃はAM5が出たばかりで、CPUもマザーボードも高価だったので5000番台で組んでしまいましたが、現在は比較的価格が落ち着いてきています。
コア数やスレッド数は変わっていませんが、周波数がわかりやすく向上していますので、これから組む人は新型の7000番台も有力な選択肢になるでしょう。
ハイエンドCPUの選び方(2020年2月現在)
- ハイエンドCPUは予算が潤沢な人向け。
- 動画編集などであればコア数の多い商品が優位。
- 内蔵GPUだとCPU性能を活かせないと思う…。
- そもそも1台目にハイエンドって冒険しすぎじゃない?
初めての自作PC、CPUの選び方まとめ。
初めてPCを組むというのにいきなり1万字も読まされた方には申し訳ない気持ちでいっぱいなのですが、結局どれがいいとか悪いとかは個々人の用途によって変わってきますので一概にいえないのが辛いところです。
CPU選びの流れとしては、
- 組んだPCで何をするかを考える。
- 決まった用途(やりたいゲームの推奨環境など)と予算で決める。
といった感じです。
そしてシリーズを決めた場合、同シリーズ内で型番の数字をどれにするかというのは初めて組む際にはあまり気にしなくていいと思います。
GPUの有無は決めておいたほうがいいですが、あとはざっくりと世代がなるべく新しいほうがいい程度の絞り方で問題ありません。
正直な話、例えばCore i5で選ぶなら13400と13500で迷うのは特に意味はありません。
13400を買ってパフォーマンスに不満があった場合、「13500にしておけばよかった」とはならず、「i7にしとけばよかった」となるからです。
それよりもGPU絡みで無印にするかFモデルにするかで考えるほうが大切ですよ。
個人的な意見としては、多少ゲームをするのであれば3シリーズ以上で組んだ上で、安めでも別途グラフィックボードを挿すのがおすすめです。
なのでCore i3ならFモデル、Ryzen3なら無印がいいですね。
内蔵GPUと専用グラボの性能差は思っている以上に大きいですからね。
逆にゲームや動画編集などを全くせず、書類作成の延長程度の用途であればCPUもGPUも性能を必要としないのでGPU内蔵型の3シリーズまでで充分と言えるでしょう。
そうなるとi3の無印かRyzen3のGモデルという選択になります。
そして予算との兼ね合いですが、かなりざっくりですがミドルレンジの場合、CPU費用は総予算の20~25%以内に収めておいたほうがいいです。
例えば10万円で組みたいのであればCPUにかけられるお金は25,000円くらいが限度になります。
ローエンドであれば比率はもっと下がり、逆にハイエンドであればもう少し比率は上がるかもしれません。
というのもCPUを高性能にした場合、それに付随して他のパーツのコストもどんどん上がってくることになるんですね。
高性能のCPUを活かすにはメモリ容量も大きくする必要がありますし、グラフィックボードの性能も要求します。
すると電力を確保するために電源容量も大きくしなければいけません。
ことパソコンに関しては、CPUにお金をかけた分を他で節約しようとするとPC全体のパフォーマンスが落ちてしまうわけです。
ですので予算オーバーを避けるためにもCPUだけにお金をかけるという選択肢は捨ててください。
何にせよCPUはパソコン全体の性能を方向づける重要なパーツです。
それ故に選ぶのも難しいですが、予算と性能とにらめっこして唸るのも楽しみの一つではありますのでぜひ皆さんも楽しみながらCPUを選んでください。
以上です!
↓内蔵GPUありCPUの個人的なおすすめ(ミドルレンジ初心者向け)
↓別途グラボを買うならこの辺?
↓性能が少し物足りなければ(ミドル)